2009-01-05(Mon) [長年日記] [Edit]
■1 2008年のふりかえりと2009年のガイドライン
2008年に書いた日記をざっと読み返して棚卸ししようと思ったら収拾つかなくなってきた。日記を「(あとで書く)」とすら書いてない日付周辺のことは全然思いだせない。このことから2009年最初のガイドラインが導き出される:
- 自分のやったことは適宜まとめておく。(あとで書く)でも構わないから、とにかく書いておく。
特に2008年の年初に目標とかは書いていなかったようなのだけれど、RubyKaigi2007で家庭内のフォースの調和を乱して以来、フォースの調和がずっと個人的なテーマだった。まだまだやるべきことや配慮すべきことはあるのだけれど、まずまずだったかな。まだ時々調和を乱すことがあるけれども。ここから、次のガイドラインが導かれる:
- フォースの調和を忘れるな
これは2年続いてガイドラインとなっているので「価値」として定着させるべきかもしれない。
ざーっと自分の2008年のエントリを読み返すと、多いのはイベントの運営とか参加とか発表のこと。あとは自分の執筆とか記事とか(雑誌や書籍、kakutani.comじゃないサイト)、ときおり技術書の紹介、ほんのちょっとだけ自分の書いたコードこと、という感じ。ここらへんは切り口ごとに別途まとめておきたい。これはガイドラインというよりも具体的なTODOに近くなるのだが:
- もっとコードを書けるように色んな段取りをする(心技体+時間)
- 作業が止まっているあのプロジェクトを再開する(しないとマズイ)
これを実現するために改めて「やらない」と宣言すべきことがひとつある:
- いくつかの例外を除いて、執筆は引き受けない
いくつかの例外: 既に引き受けてしまっているもの、自分でやると既に言ったもの、るびま。
ま、そうはいっても依頼なんてそうそう来ないんだけど、先日たまたま、ちょう久しぶりに依頼が来たので、ここでも改めて書いておきたいと思った。
最後のガイドライン。2008年には世界が意味に満ち満ちる体験をしたので、
- 2008年よりもいきいきと世界の意味を体験できるようになる
今年もよろしくお願いします。
■2  LEGOシティ ごみ収集車
LEGOシティ ごみ収集車
息子が妻の職場の人からクリスマスプレゼントをもらったらしく、帰宅するなり一緒に組み立てることになった(半分だけ)。半分だけ完成した状態で息子は彼自身の電池が切れるまで遊んでた。
2009-01-06(Tue) [長年日記] [Edit]
■1 2008年のkakutani.comのアサマシランキング
2008年のふりかえりっぽいネタも入れつつ、恒例行事を。
2007年のkakutani.comのアサマシランキングと見比べるとあまり代わり映えしないが、2007年には1冊もランキングに入ってなかった翔泳社の書籍が2冊ランクインしている。でもこれは「翔泳社の書籍」というよりは「青木靖さんによる訳書」だな。野口さん去りし後、kakutani.com的には今後はどうかな。
いっぽうオーム社の書籍は2007年の4冊から1冊減って、2008年は3冊になってしまった。がんばれ、日本オーム社の会。では1位から順番に:
1位 『実装パターン』
『実装パターン』
2008/12/08の紹介(しかも大したこと書いてない)にもかかわらず1位になった。お前らはKentBが好きすぐる。
実は私は翻訳はまだ読み終えてないのだけれど(いま8章)、これまでのところ翻訳はわりと良いかんじ。KentBっぽい語り口になっているところもあって素敵なところもちらほら。細かいところで気になることはあるけれど、細かい話なので、気が向いたらはてなグループ(こちらもよろしく)にでも書きたい。
ちなみに「訳者あとがき」によれば:
最後に,本書は永田渉氏による翻訳であるが,今回は株式会社ピアソン・エデュケーションの新しい編集者として村田豪氏が担当し,細かく丁寧に手を入れてくれたことに感謝する.
とのこと。訳者あとがきについて言いたいことはあるけれど、それはまたいずれ。
最後に、2008年も10位にランクインしている原著の書影も紹介しておきますね。
2位 『アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣』
『アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣』
昨年は1位。今年は僅差で2位でした。fkinoと監訳。オーム社(オーム社!)から刊行。サポートページもあります。
刷数をジリジリ増やしてもらったおかげでとはいえ、1年間で5刷まで達したのには驚いた。あと、「増刷」と日記に書いたらyomoyomoが釣れてコーヒー吹いた。
2009/01/07追記
われらがジュンク堂書店池袋本店のコンピュータ書の年間ランキングで4位だそうな。すばらしいね。
3位 『The Ruby Programming Language』
『The Ruby Programming Language』
各章の扉絵が_why画伯なことはもちろん、本サイトではあのartonが絶句した一冊としてあまりにも有名。本書は翻訳作業も進行中らしい。1.9.1RC1リリースと同じ頃に翻訳が出版されたりすると素敵だなあ。
ちなみに、ランキング的には2位と3位のあいだに越えられない売上冊数のギャップがあります。
4位 『Eric Sink on the Business of Software 革新的ソフトウェア企業の作り方』
『Eric Sink on the Business of Software 革新的ソフトウェア企業の作り方』
受託開発をやってる身にとっても考えることのヒントはたくさんあった。その結果はまだ出せてないけど。
5位 『My Job Went To India オフショア時代のソフトウェア開発者サバイバルガイド』
『My Job Went To India オフショア時代のソフトウェア開発者サバイバルガイド』
3年にわたってランクインしている。2006年は5位、2007年は7位。kakutani.com推薦図書としては殿堂入りの1冊。オーム社(オーム社!)刊行。2008年はChad FowlerがRubyKaigiに遊びに来てくれたのでサインもらった。RubyKaigi2008のジュンク堂書店RubyKaigi店でも3位だった。
書籍の内容と対象読者層の広さは『アジャイルプラクティス』より売れてしかるべき一冊。ちなみに私は原著・訳書・訳書の合計3冊保有。今年も売れろ!!!
6位 『アジャイルレトロスペクティブズ 強いチームを育てる「ふりかえり」の手引き』
『アジャイルレトロスペクティブズ 強いチームを育てる「ふりかえり」の手引き』
2007年はランク外だった(ちゃんと紹介してなかったのかも)。kdmsnr翻訳、オーム社(オーム社!)刊行。
id:k3cも「今まで読んでなくて、正直、すまんかった。後悔している」と書いている。今年はもっと後悔する人たちがもっと増えればいい。
7位 『Scripted GUI Testing with Ruby』
『Scripted GUI Testing with Ruby』
Pragmatic Bookshelfのシリーズ。公式サイトは、 http://pragprog.com/titles/idgtr/scripted-gui-testing-with-ruby
翻訳の予定はないのかなあ。
8位 『BEST SOFTWARE WRITING』
『BEST SOFTWARE WRITING』
おもしろかった。厚切りベーコン!!
9位 『10+1 No.48 (48)』
『10+1 No.48 (48)』
2007年は10位だった、江渡さんのインタビュー掲載誌。世界の意味を知るための一冊。
あわせて読みたい:
10位 『Implementation Patterns』
『Implementation Patterns』
2007年は3位。2008年1位の『実装パターン』の原著。
10位 『Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship』
『Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship』
10位は2冊あって、こちらはUncle Bobの新刊。1位の『実装パターン』とあわせて読みたい1冊。
圏外からの一冊: 『インターフェイス指向設計』
『インターフェイス指向設計』
自分が監訳した書籍なのに13位だった。出版前後の時期にバタバタしていてきちんと言及できずにRubyKaigi戦線に突入してしまい、色んな対応が後手後手に回ったのがよくなかった。反省。
印刷所に入稿されてからが著者(監訳だけど)の本当の仕事ははじまる。読者の手に届くようにするまでが書き手(監訳だけど)の仕事なのだ。といっても何もしなかったわけではなくて、今回は新しい試みとして、Twitterで献本を募集したり、オライリー・ジャパンの書誌情報のページをブクマしていたひとに献本したりしてみたのは良かった。次回以降も機会があれば試したい :-)
ランキングでは13位だけど、いちおう増刷されてます。ただし2刷は緊急増刷だったので、サポートページの正誤表にあるバグの修正を反映できませんでした。すみません。こんな状態にもかかわらず、那須のほうで読書会を開催もらえているもよう。とてもありがたい。
2009年も素敵な書籍に出会えて、そしてアサマしくもたくさん売れるといいな。
2009-01-08(Thu) [長年日記] [Edit]
■1 Keynote'09用にリモコンを新調した
Keynote'09で新しいリモコンがサポートされたみたいなので購入したのが届いた。

折りしも今日、プレゼンテーションする機会があったので、さっそく使ってみた(そのときの機体はemeitchのiPhoneを借りた)。
これはヤバイwwwwww
もうちょっと詳しくあとで書きたいなあ。それにしても、いまどきのプレゼン用のリモコンは動画を観たりリブログしたり、IRCまでできるようだ。21世紀すごい。
どうやら先代のリモコンは2007-03-23に到着したようだ。1年10ヶ月おつかれさまでした。
2009-01-09(Fri) [長年日記] [Edit]
■1  翻訳書『アジャイルな見積りと計画づくり 価値あるソフトウェアを育てる概念と技法』を出版します
翻訳書『アジャイルな見積りと計画づくり 価値あるソフトウェアを育てる概念と技法』を出版します
arton とtakaiのはぐれ悪魔超人コンビみたいなタッグによる書き下ろしには敵わないかもしれないけれど、私と同僚の安井さんとで翻訳した新刊が同じ時期に発売するでお報せします。細工も流々なので、いちおう書影も掲載されてます。皆さんどんどんアサマシリンクをどうぞ!! 今回の版元は毎日コミュニケーションズです。他のオンライン書店ではcbook24にも出ているようです。
『アジャイルな見積りと計画づくり』はMike Cohnの『Agile Estimating And Planning』の翻訳です。原著がこの日記を書いている時点で5,148円なのに対し、訳書は3,360円(税込)というお求めやすい価格でのご提供となっております :-)
毎コミの本書紹介のページで、書籍の「イントロダクション」の一部と「訳者あとがき」の冒頭、それから目次が読めます。分量は少ないですが、翻訳のクオリティ判断の参考にしていただければと思います。
書籍ぜんたいの内容については「訳者あとがき」にも書いたけど、本書は安井さんや私が過去3年間に関わってきた様々なプロジェクトでの提案や立ち上げ、見積り、計画づくり、運営のネタ元でした。なので、これから私たちは位置エネルギーを利用した優位な立場に立てなくなります。つまり本書は(安井さんはともかく少なくとも)私じしんにとっては、今後の自分の身の振り方を考えざるをえなくなる一冊です。
けれども、もしも私の仕事が消滅するぐらいに、日本中のソフトウェア開発プロジェクトの見積りと計画づくりがアジャイルになったとしたら、そんな世界はさぞ素敵でいきいきとしているだろうなと思います。本書をきっかけにそんなプロジェクトが増えていくかと思うと、すごくわくわくします(私のなかではそういうことになってます)。
本書を読んだソフトウェア開発の発注者、営業担当、経営陣にプロジェクトマネージャ、現場のリーダーに開発者といった皆さんは、きっと本書の内容をおのおの持ち場で役立てられると私は確信しています。どうぞご利用ください。
サポートページは準備できたら別途アナウンスします。
 Mike Cohnとバーンダウンチャートと私(抄)
Mike Cohnとバーンダウンチャートと私(抄)
長くなったのでセクションを分けます。個人的に、今回の仕事を通じてMike Cohnを日本のアジャイル界の皆さんに紹介できることも光栄に感じている。
『アジャイルな見積りと計画づくり』の原著者であるMike Cohnの前著は『User Stories Applied: For Agile Software Development』で、私はこれを読んでバーンダウンチャートをはじめたのでした。これを世界のケンジは「おそらく日本最古のバーンダウン」と言ってるけど、たぶんもっと古いものはあるんじゃないかな。ただ、日本のアジャイル界に事例として放流したのは私だと思う。2004年7月。
『User Stories Applied』はいまだに翻訳がなくて哀しいなあ。5年前に某社の編集さんに話を振ったときにはスルーされたけど、現場の皮膚感覚としては、そろそろ日本に紹介してもいいかもしれない。原著の出版から5年経ってるけど、洋書で類書は結局出てないのは、誰も本書に勝てないからじゃないかなあ。しかも、Kent Beck Signatureシリーズの記念すべき1冊目。もはやアジャイル界の古典ですよ。もしどこも手を着けないようでしたら翔泳社さん、いかがでしょうか ;-)
2009-01-10(Sat) [長年日記] [Edit]
■1 
 『プログラミング言語Ruby』は1/26発売
『プログラミング言語Ruby』は1/26発売
これはRuby 1.9.1リリースにぶつけてきたな……。arton x takaiの『JavaプログラマのためのRuby入門』は1/29だし。私の新刊『アジャイルな見積りと計画づくり』の発売は1/29頃なので、今月下旬はRubyがライバル。
デブサミ2009のセッションもRuby1.9リリースマネージャが裏番組だし。なんだかさいきんRubyと相性が悪いです!!!
でも、『Head First ソフトウェア開発』のオライリー・ジャパンのサイトでの関連書籍がRubyばかりなことからもわかるように、Rubyとアジャイル開発は仲良しのはずなんだ。どうやらHead Firstシリーズでは「ソフトウェア開発 == アジャイル開発」という立場らしく、目次を見た限りではかなり期待できそう。
■2 妻がiPhoneに機種変更した
ちょっとリモコンを使ってもらったら気にいったようで、早速機種変更していた。iPhoneで電話してる人をはじめてみた。
■3 「新春座談会 このコンピュータ書がすごい! 2009年版」の本編を聞けなかった話
「献本をもらったくらいでもう一冊買わないのは素人」という発言で(私のなかでは有名な)id:takahashimのトークセッション(ぼくは素人でいいです)。
これは西のid:naoya、東のid:takahashimですよ!!と個人的には勝手に鼻息が荒かったんだけど、いろいろあって息子を預けるアテがなくなったので本編を聞くのは断念。
息子とふたりでジュンク堂まで行くだけ行って、ホンモノのオーム社の営業の方の名刺をいただいたり、お世話になってる出版社の編集の皆さんに挨拶した後、8Fに行って機関車トーマスの絵本を買って帰ってきた。まあ、息子をジュンク堂デビューさせられたのでよしとする。あと、往復で山手線を一周した。
トークセッションについては後日動画が公開されるらしいので、それを楽しみにするとしよう(オライリーさんがんばって)。また、当日のustは技術評論社さんだった模様。ええと、id:takahasimの日記からメモラブル・クォート:
ある意味、「コンピュータ書」というのは、特異な位置にあると思います。コンピュータとネットワークの発達は、出版業界から見れば、巨大な「敵対勢力」のように見えるのは間違いないでしょう。にも関わらず、そのコンピュータとネットワークに携わる人々にとって、欠かすことのできない情報のライフラインとして、「コンピュータ書」が現状機能しています。少なくともこの国の情報産業、そしてコンピュータとネットワーク関連技術は、出版のエコシステムが機能不全に陥れば、無傷でいられるとは思えません。一種「獅子身中の虫」にも似ています。
その一方で、このような特異な位置にあるということは、上手く利用すると、コンピュータと書籍に関する様々な試みを行うことも可能になるということでもあります。実際、今回のイベントでも、オライリーさんや技評さんが動画撮影や配信を試みたりもしていました。このような試行錯誤の先に、コンピュータと書籍とのあるべき関係の未来があるはず、という気がしています。……ちょっと大げさに言えば、そのようなことを考えさせられたトークセッションでした。
2009-01-14(Wed) [長年日記] [Edit]
■1 デブサミ2009開発プロセストラックのコンテンツ委員としての立場を離れて言う。おまえらは2/12(木)はこのセッションに参加しろ
2/12(木)のタイムテーブルから、全時間帯じゃないけど:
- 11:00〜11:55【12-C-2】「未来へつながる言語〜ある言語おたくの視点から」 まつもと"言語おたく"ゆきひろ
- 13:10〜14:00【12-B-3】「Ruby1.9の現状と導入ポイント」 Yugui
- 15:25〜16:15【12-B-5】「ブラウザJavaScript高速化JITバトル最終決戦」 森田創(omo)
- 17:14〜19:10【12-C-7】「株式会社はてなの開発戦略」 id:secondlife
- 17:14〜19:10(↑の裏番組)【12-D-7】コミュニティから選出のLT大会 id:hyoshiokと着物のドラ娘(id:objectclub)
会場にはオライリー・ジャパンがブース出展しているはずなので、下記2冊を買ってサインをもらうことも可能なはず(というか日本Rubyの会のブースの展示物にしたい)。
まだ「調整中」のセッションのある時間帯は(ごめんなさい、他ならぬ開発プロセストラックにも調整中があります……)、あとから分割して申し込んでしまって、自分が聞きたいと確定しているセッションは早めに申し込んでしまえばいいと思う。受講セッションの管理が若干煩雑になるけれど、そのほうが確実。
それから、デブサミ2009の公式タグは存在しないようなのだけれど(そんなことではいけないと思います!)、岩切さんからdevsumi2009でどうか、というつぶやきがでているので、感想などをブクマするときはこれでよろしくです。
「コンテンツ委員としての立場」からのおすすめは「調整中」じゃなくなってから、あとで書く。2/13(金)についてもあとで。
2009-01-23(Fri) [長年日記] [Edit]
■1  『プログラミング言語Ruby』出版記念トークセッション懇親会のおしらせ
『プログラミング言語Ruby』出版記念トークセッション懇親会のおしらせ
ruby-list:45799でアナウンスされているように、2/12(木)(デブサミ2009の初日とカブってる)に、ジュンク堂書店新宿店でMatzとmputによるフラナガン本発売記念トークセッションが開催されます。
これにあわせて、幹事のtakaiから既にruby-list:45802でアナウンスされている通り、トークセッション終了後に懇親会も予定されています。
Matzとmputを囲む懇親会というのも珍しいと思います。懇親会からの参加も問題ありません(事実、デブサミ2009からの合流組もそれなりにいる)。トークセッション本編に参加される方はもちろん、デブサミ2009に参加される方も、19:00に新宿のトークセッションなんていけねーよ、というお仕事がお忙しい皆さんも、ふるってご参加ください。
2009-01-24(Sat) [長年日記] [Edit]
「いまや、標準語は政治を語ることばに堕してしまい『人生を語ることばは方言しかなくなってしまった』のである」。
仙台Ruby会議01は、運営委員長のid:yuichi_katahiraが周囲を巻き込んでいるような、氏じしんが巻き込まれているような、素敵な共犯関係で成立していた。参加者/発表者/運営の皆さんのレポートや感想ははてブのタグがよくまとまっているのでそちらを。イベントのフィードバックはこうやって集めるんだね。
本編ではみんな、多かれ少なかれ自分(たち)とRubyとの関わりを語っていた。それがすんなり受け入れられる空気は、Regionalの魔法のひとつなのかもしれない。語りはどれも標準語だったけど。
九州Ruby会議01に参加して、「カンファレンスは現場だ」と暑苦しく語ったヒゲのおっさんがいる。takedasoftが口火を切ってはじまったライトニングトーク全体の流れがうみだした、非東京と東京のハックとコミュニティとが入り混じった感覚は、10月から結果的に連綿と続いているRegional RubyKaigiの「いま」を切り取っていたと思う。
仙台でも素敵な人たちと素敵なごはんに巡りあえました。ほんとうに行ってよかった。みなさんに感謝します。ありがとうございました。
■1 仙台Ruby会議01でのLT:「日本Rubyの会のほうから来ました」
しゃべってきた。写真はtakaiのFlickrから借りてます。
ぼくも明るい単焦点がほしいなあ。仙台にはズームなレンズを持っていって失敗した。以下、発表資料です。こんかいも最後までめくれず。色いろと言い訳はできるんだけど、やめとく。せっかくレオのスライドをパクったのになあ。
2009-01-25(Sun) [長年日記] [Edit]
派手に寝坊したのにCTC光画部と社長ふたりとAsakusa.rb主宰のフェロー(笑)が相手してくれたので、るーぷる仙台にのってぐるりと一周(小一時間乗ってると社内アナウンスがだんだん「Google仙台」とか「ルーブル仙台」に聞こえてくる)。青葉城からの見晴しがきもちよかった。駅まで戻って、日本酒と海の幸とスシをキメてからMAXやまびこ自由列で帰宅。自由席はほんとにフリーダムで快適。よく寝た。
■1 Upcoming Regional RubyKaigis
Regional RubyKaigiは昨年の10月の札幌01、11月の関西01、12月の九州01(ああ。感想かいてない)、そしてこの週末の仙台01と毎月続いているのだけれども、2月もあります。それもふたつ:
2/2(月): 松江Ruby会議01
島根大学のプロジェクト研究と、パネルディスカッション。パネルディスカッションではRubyの今後がテーマ。メンバーがものすごく豪華。「会議」っぽい!!
現場に行けないひとは、Ustream.tvでの配信もチェックするとよいかも(ただし、配信品質はベストエフォートです)。
2/21(土): とちぎRuby会議01
RubyKaigi2008でのいけざわさんによるLT「toRubyでみつけた Rubyist人生再出発」(公式, RubyKaigi日記)で一躍有名になったtoRubyの皆さんが中心になっての開催。咳さんや「バカが征く」の中の人にも会えます。RubyKaigiの別実装よりもtoRubyであることを重視するそうです。toRuby is nice.
2009-01-26(Mon) [長年日記] [Edit]
■1 「Javaの掟・Rubyの掟~寝ても起きてもプログラミング~」トークセッションのおしらせ
arton関連書籍の刊行を記念して、artonファミリー総進撃のトークセッションが:
- 2/5(木)の19:00から、
- ジュンク堂書店池袋本店で
開催されます。arton! るいも! takai! (なぜか)id:takahashim!
- http://www.junkudo.co.jp/newevent/evtalk.html#20090205ikebukuro
- http://d.hatena.ne.jp/takahashim/20090123/p1 (高橋さんが↑をコピペしてくれている)
刊行が記念されているのは以下4冊(!):
 『コーディングの掟(最強作法) 現場でよく見る不可解なJavaコードを一掃せよ!』
『コーディングの掟(最強作法) 現場でよく見る不可解なJavaコードを一掃せよ!』
いまやすっかり業務Javaプログラマではなくなった私だけれど、タイトルと著者陣から察するに、おなじ翔泳社の『Javaプログラミングの処方箋』と似たテイストで、もっとコーディングに寄せるけど、『実践Java』に比べると現場寄りみたいなポジションを期待している。
いま書いたように私はもはや業務Javaプログラマではなくなってきたので、手持ちのJava関連書籍は捨てるか知人にあげているのだけれど、artonさんとるいもさんのこの2冊はいまもキープしている。当日はるいもさんの話をはじめて聞けるのが楽しみ。
 『JavaプログラマのためのRuby入門』
『JavaプログラマのためのRuby入門』
私たちの新刊と同時期発売のはぐれ悪魔超人コンビによる新刊。これも実物を手に取ってない(当日ジュンク堂で買おうと思ってる)のでわからないけれど、仙台Ruby会議01では「8割artonが書いてる」というウワサを小耳に挟んだけど、気にしない。
本書に期待することは「JavaからRubyへ:プログラマ篇」だなあ。『JavaからRubyへ』のサブタイトルは"Things Everything Manager Should Know"(力およばず翻訳では「マネージャのための実践移行ガイド」になってる)なので、本書はたぶん"Things Everything Programmer Should Know"(プログラマのための実践移行ガイド)のはず。

 プログラミング学習シリーズ Ruby (1)はじめてのプログラミング, (2)さまざまなデータとアルゴリズム
プログラミング学習シリーズ Ruby (1)はじめてのプログラミング, (2)さまざまなデータとアルゴリズム
こちらはふたたびarton x るいもコンビ。Rubyでプログラミングを学ぶシリーズらしい。年若い人たちが対象だそう。実物はまだ手に取ったことがないからわからないのだけれど、artonさんからはうちの息子におすすめ、と言われた。どんなだwwww
息子がRubyかあ。
そうなったらやはり楽しいのかなあ。いま、ちょっとした(いや、かなりの……)反抗期なので、なんかいろいろ込みあげてきちゃう。息子がコードを書けるようになる頃のRubyのバージョンっていくつだろう。
2009-01-28(Wed) [長年日記] [Edit]
■1 デブサミ2009:価値あるソフトウェアを提供し続けるための「開発プロセス」のみどころ
(この日記は1/31に書いてます)
前口上
事例セッションをすべて確定させるまでにいろいろ難航してしまったこともあって、みどころを書くのが遅くなってしまった。 ようやく「みどころ」を書きあげたものの、当初公式サイトに送ったものは長くなりすぎてしまって、結果としては簡約版が掲載されている。ここは自分のサイトなので字数制限もないので、当初のものに近いかたちでみどころ――というか、コンテンツ委員として「開発プロセス」トラックをどう考えているかをもう少しくわしく書いてみたい。もっと早く書ければよかったんだけど、いろいろあるんだよね。私の本業はイベントのプロモートじゃないし……。
「開発プロセス」トラックのみどころ(ディレクターズカット版)
「開発プロセス」は今年のデブサミ2009のテーマである「つなぐ、つながる」という言葉ととても相性が良いです。そもそもソフトウェアの開発プロセスは「なにをつくるか」というビジネスの立場と「どうつくるか」というテクノロジの立場との間に橋を架ける――「つなぐ」存在です。今年の開発プロセストラックでは、それ自身が「つなぐ、つながる」ものである開発プロセスが「つなぐ、つながる」ものという切り口でセッションを用意しています。
最初のつながりは「過去と現在」です。これは【12-A-1】で萩本順三さんに「開発プロセスの心」と題してお話いただきます。
次のつながりは「理論と実践」です。開発プロセスは現場で使われてはじめてビジネスとテクノロジをつなぎます。今回はビジネス側からの視点を中心にした事例セッションを3つ用意しています。「【12-A-2】ケーススタディ:不景気と戦うシステムインテグレート」では「低コストで持続可能な開発」を、「【12-A-4】Eclipse-Way :分散アジャイル開発のためのプラクティスとその事例」では「大規模・分散開発」を、そして「【12-A-5】ユーザー企業責任で25サイトをアジャイルに開発」では、パートナー企業との協業を前提としたユーザ企業が、開発するシステムのビジネス価値を高めていくための取り組みを、、それぞれ事例を通じて紹介していただきます。
ですが、ビジネスの視点は片側からのものでしかありません。開発プロセスをうまく回していくためには、テクノロジとそれを使う人とのつながり――技術的卓越の追求も欠かせません。「【12-A-6】オブジェクト指向エクササイズのススメ」では「人とテクノロジ」のつながりについて語っていただきます。21世紀の開発プロセスに、オブジェクト指向的な考え方は欠かせません。「北風が勇者バイキングをつくった」
それから、コンテンツ委員である角谷は「【12-A-3】時を超えたプログラミングの道への道」で、ひとりの開発者と開発プロセスとのつながりについてお話しします(このイベントはデベロッパーズサミットですから)。
そして、トラック最後のセッションはパネルディスカッション「【12-A-7】『使う』と『作る』がつながるシステム開発」です。開発プロセスのつながりの未来を、SIのさまざまな面を経験されたパネリストの皆さんと一緒に考えたいです。パネリストがSI業界に偏っているとは思いますが、デブサミの客層的にはこれで良いと思っています。このパネルでは予定調和的なオチは用意していません。
開発プロセストラックの構成には、1日どっぷり開発プロセストラックにつかる皆さんはもちろん、興味があるところだけ「つまみ喰い」される皆さんにも、開発プロセス自身とそれを取り巻くつながりについて考え、行動するきっかけになってほしいというコンテンツ委員の願いを込めています。
どうぞご利用ください。
「残席僅か」フラグが立っていないセッションについて捕捉
まず、【12-A-5】ユーザー企業責任で25サイトをアジャイルに開発」。これは個人的に思い入れがある(のに「残席僅か」フラグが立ってない)。
デブサミの準備の一環としてコンテンツ委員である私は次のようなアジャイル開発の事例を探す旅に出たのだった:
- 完全内製ではないユーザ企業が、
- 自社システムのビジネス価値を高めるために、
- アジャイル開発の考え方を自分たちの現場に適用させる試みを組織的に、
- 年単位(こんかいの事例では3年)で取り組んでいる
当初はすぐ見つかると思ったのだけれど、なかなか講演依頼を引き受けていただけるところまでたどり着けなかった。もうだめかも……と思っていたところに快諾いただけたのがリクルートさんでした(これも半ば押しかけるようなかたちで依頼した)。今回の事例が唯一無二の正解というつもりはないけれども、自社のビジネスの根幹を真剣に考えて組織的に実践したひとつの事例として、発注者/受注者双方にとって考えるヒントは満載のはず。
それから、「【12-A-2】ケーススタディ:不景気と戦うシステムインテグレート」も残席僅かフラグが立ってない。FileMakerはプロプライエタリ製品だけれども、低コスト化、セルフビルド、開発の持続可能性といったテーマは開発のプロセスを考えるうえでは今後ますます重要になってくる視点だと思う(私じしんが何かを語るには3年以上早いテーマ)。
関連リンク
2009-01-29(Thu) [長年日記] [Edit]
■1  『アジャイルな見積りと計画づくり』が発売されました
『アジャイルな見積りと計画づくり』が発売されました
(このエントリは2/3に書いてます)
人生初の肉の日リリース!!――って、書籍だけど。おかげさまでAmazon.co.jpでは出荷開始っぽい29日の午後から24時間以内にランキングは瞬間最大風速で総合348位まで食い込むことができ、またAmazonへの初回入荷ぶんは初日で全部売り切ったようです(この日記を書いている時点ではまた「在庫あり」に戻っている)。お買い上げいただいた皆さまありがとうございます。
今回もサポートページも用意しています(さっそくバグが……)。ネットで見つけた本書にまつわる感想などは「AgileEnP」タグではてブにブクマしています。本書を読んで「イイネ」と思われた方は、ご自身のブログに書いていただくのはもちろんですが、hsbtの素敵な提案にご協力いただけると嬉しいです:
レビュー書いた人は Amazon にレビューをそのまま投稿した方がいいように思う。feed reader で追っかけたり、角谷さんのブックマークを追っかけたりしないような層向け。
もうひとつの訳者あとがき
訳者あとがきに書ききれなかった話を少しだけ。
まず何よりもこんかいは、同僚の安井さん(ちょう英語ができてAgile2008でも大活躍)と組めたからこそ最後までやりとげられたと思います。ここまで来れたのは、いろいろ自分に言い訳しながらムラのある私と違って、きちんと仕事を進めていく安井さんのおかげです。もちろん、私たちの作業を最終的に書籍へとまとめたのは毎日コミュニケーションズで編集を担当してくれた伊佐さんの忍耐あってこそなのですが。伊佐さんには土壇場になってのドラスティックな変更依頼をかなり拾っていただきました。ほんとうにお疲れさまでした。しかし、書籍もソフトウェアも、マーケットに出てからが本番だということを、つくづく感じています。これからが本番です。がんばりましょう :-)
それからもちろん、今回も堪忍袋の緒を何本も何本も切りながら、それでもフォースの調和の道を一緒に探してくれた妻と、私を信頼してくれている息子にも感謝します。ありがとう。
そして最後に個人的な告白を。本書の翻訳と、それ以前での原著を読んで実践することは、私にとっては那須のケント・ベックの言葉を自分じしんのものとするための旅路でした。具体的には次の2つです。「好きなプラクティスは『計画ゲーム』」「見積りのコツは『見積りつづけること』」。
本書の翻訳を終えたいま、私はこの言葉の意味するところを自分じしんで理解できたと思っています。そして、本書の翻訳の内容はきっと咳さんにも納得してもらえるものだという自信があります。デブサミ2009なりとちぎRuby会議01で咳さんから本書の感想を聞けるといいな、と思ってます。
もちろん、咳さん以外の皆さんからの感想もお待ちしております。どこかで見かけたらお気軽に声をかけてやってください。社内勉強会とか読書会を開催されるのであれば教えてもらえると嬉しいです。
あと、安井さんはデブサミ2009では私の裏でしゃべります(デブサミは「裏番組が……」みたいなの多いね)。カードゲームは安井さんが最近熱心に取り組んでいて、私のgdgdな電波セッションなんかよりもよっぽど役に立つと思います。
それでは。よい見積りと計画づくりを。
2/4追記: PDFを「立ち読み」できるようになっていました
毎コミさんのサイトで、部分的にですがPDFを「立ち読み」できるようになっていました(ありがとうございます!)。 購入にあたっての参考にしてもらえると嬉しいです。
以下の内容を立ち読みできます。合計30ページほど。
- 日本の読者に向けて、まえがき、著者紹介、謝辞
- 目次
- イントロダクション
- 第1部 1章
- 訳者あとがき
どうぞご利用ください。
2009-01-31(Sat) [長年日記] [Edit]
■1  Ruby 1.9.1 リリース!
Ruby 1.9.1 リリース!
(この日記は2/4に書いてます)
開発チームの皆さまおつかれさまでした!! くわしくはruby-lang.org のニュースとかruby-list:45836とか、近日中にリリースされるるびま0025号を。あたらしいリファレンスマニュアル(るりま)は、okkezさんところから持っていくのがわかりやすい。海外での紹介だと……Ruby Insideの記事が良いのかな? Peter Cooperが関連リンクを手際良くまとめてます。
「あわせて参加したい」
1.9に関しては、雰囲気で使っている程度なので技術的なことはほとんど書けないので(ここで馬脚をあらわす)、プロモータ業的なことを2つ3つ:
まず、1.9.1リリースをお祝いしたい方は、このタイミングで出版された「Rubyの新しいバイブル」フラナガン本の出版記念トークセッションの日が狙い目。トークセッションは大阪も東京も満員御礼みたいだけれども、懇親会はまだ参加の余地がある模様:
- 大阪(2/5): http://cotocoto.jp/event/29232
- 東京(2/12): http://atnd.org/events/297
自腹のリリースパーティだと思ってトークセッションの懇親会に参加してみるのはいかがでしょうか。東京に関しては、takaiが余興をどうするのかをとても楽しそうに考えてました。皆さまのご参加お待ちしております。
また、東京のジュンク堂新宿店でのトークセッション当日のデブサミ2009初日、2/12の13:00からはリリースマネージャのYuguiさんから「Ruby1.9の現状と導入ポイント」というセッションがあるので、1.9で何がどう変わったのかに興味のある方は是非ぜひこちらのセッションにもご参加ください。前にも書きましたが、デブサミ2009→トークセッション懇親会という参加ルートもアリです。




 リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大)
リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大) 『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』
『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎)
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎) 実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘)
実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘) The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ)
The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ) アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未)
アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未) JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)
JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)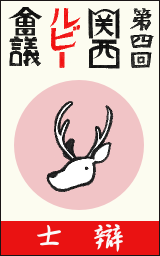



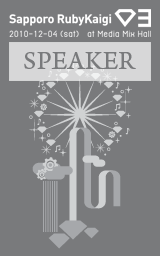






○ zunda [あわわわ > 執筆は引き受けない。るびま、フォースの調和とコード書きを乱さない範囲でどうぞよろしくお願いします]
○ かくたに [るびまは「自分でやると決めたやつ」なので問題ないのです :-)]