2009-02-01(Sun) [長年日記] [Edit]
■1 デブサミ2009:満空情報を見ながら個人的な13日(金)のオススメを書いてみる
(この日記は2/4に書いてます)
そんなことより自分のセッションをどうしたらいいのか途方に暮れているのだけど……。
【13-D-1】ERP5に見るストレージ技術
奥地さんだぜ? みんな聞かなくていいの?
 【13-E-2】アート・オブ・アジャイル デベロップメント 〜テストが駆動するビジネス価値〜
【13-E-2】アート・オブ・アジャイル デベロップメント 〜テストが駆動するビジネス価値〜
TAOADの監訳者にして同僚のfkinoがid:t-wadaトラックに乗ることになって、困ってる(ネタがかぶってるという意味で)。概略レベルでは内容をニギっていて、fkinoは地に足がついているの担当で、私は電波担当……なんだけど、幻視力発電所の出力が足りないので電波出るかどうか不安。困ってる。
 【13-D-3】プロとしてのOracleアーキテクチャ入門 〜 番外編 〜
【13-D-3】プロとしてのOracleアーキテクチャ入門 〜 番外編 〜
休眠中の:-)PofEAA読書会で「エンタープライズっつたらバッチだろ」とWRサーガを語ってくれていた渡部さんがOracleの人になっていた。裏番組のid:cactusmanのセッションは「残席僅か」になってるので、ならばぼくはWRをオススメします!!
 【13-E-4】「レガシーコード」とはいったい!? 〜あなたも書いてるかもしれないレガシーコード〜
【13-E-4】「レガシーコード」とはいったい!? 〜あなたも書いてるかもしれないレガシーコード〜
Working Effectively with Legacy Code(WEwLC)読書会のコアメンバーの皆さんによるセッション。WEwLC読書会は結局2回しか行けなかったけど、そんな私でもあたたかく迎えてもらえました。そういえば、当初t-wadaの日記で読書会をアオっていた人たちの実際の読書会参加率ってどれぐらいいるんだろう。
【13-*-5】パス
これはひとつに絞れない。
【13-A-6】ひよこクラブ ver.Engineer
なんぞwww
2009/02/05追記
 【13-E-7】パネルディスカッション:テストを行うこと、テストを続けること
【13-E-7】パネルディスカッション:テストを行うこと、テストを続けること
裏番組がどれも気になるのだけれども、やっぱり私はid:m_sekiとid:t-wadaと太田さん、だな。id:objectclubがんばって。
あわせて読みたい
2009-02-02(Mon) [長年日記] [Edit]
■1 松江Ruby会議01に行ってきた
(この日記は2/9に書きました)
今度は松江。主催は島根大学。開発合宿と併催だったので、パネルのメンバーがちょう豪華。Matz,ko1,akr,nobu,yugui,mput,knu,shugo。すげえ。*RubyKaigi* に武者さんが登壇したのはこれが初めてだと思う。かっこいい。ぼくはミーハーなので最前列で眼福眼福。こんな布陣で開催できるのは松江ならではだな、と思った。
パネルはRuby1.9.1リリース直後だったからか、全体的にまったりした感じ。mputがナイスだった。パネルのお題にあった「Ruby1.9.2に向けて」という意味では「RubyKaigi2009でロードマップを発表したい」とのこと。いまのtrunkが1.9.2になるという認識で合ってるんでしたっけ……。るびま0025の「Ruby1.9.1の歩き方」に1.9.1への移行パスの話などをzundaさんがまとめてくれました。さすが神ロガー。
るびまにもリンクがあるけれど、当日のUstream.tvでのストリーミングは録画されているようなので、そちらもどうぞ:
yharaセンセイの「そうそうたるメンツ...と聞いて、新ネタでLT」という態度がスバラしいな、と思った。私は野田先生から「何かLTやって」と話を振られたけど全力で断わってしまった。腑甲斐なし。
■2 次のRegional RubyKaigiは、とちぎRuby会議01
で、次のRegional RubyKaigiはとちぎRuby会議01。2/21(土)。演題は決定していないみたいだけれど、招待講演で誰がしゃべるかは決まった模様。原先生とごとけんさん。咳さんのことばを引用しておくと:「このメンバーで連想するのは20世紀の末に行われたLinux Conference 2000 fallです。プログラムには原さん、gotokenさん、咳の名前があります。池澤さんも参加されていたそうです」とのこと。伝説ふたたび。
参加者リストは公開されていないけれど、懇親会がATNDなので、誰が参加するのか凡そ把握できるようになっています。tkoは「バカが征く」の中の人ね。東京01の発表者や、仙台01の首謀者の名前もみえる。
2009-02-03(Tue) [長年日記] [Edit]
(この日記は2/9に書きました) Matzにっきの次の日もやってたので、ちょっとだけ覗かせてもらった。二度寝してチェックアウトぎりぎりにホテルを出たのでほんとちょっとだけ。もっと早く行って見学したかった。
空港までのバスはふたりで貸切だった。なかださんはホントにどこでもhackするんだなあ、と思った。
2009-02-07(Sat) [長年日記] [Edit]
■1 Rubyist Magazine 0025号 リリース!
(この日記は2/10に書いてます)
リリースおつかれさまでした。RSpecの記事は今回もお休み(書きあげられなかった)。Ruby 1.9.1総力特集とカンファレンスやコミュニティ、Regional RubyKaigiレポートなど、2009年陽春のRubyが濃縮されているかんじ。ちゃんとゴルフもある!
毎コミさんから読者プレゼントに『アジャイルな見積りと計画づくり』を提供してもらいました。Rubyを使ったアジャイルなプロジェクトでも計画と見積りは大事だと思います。どうぞご利用ください。
デブサミが終わったらちゃんと読む。
■3 まつもとゆきひろが語るBeautiful Code × エンジニア35歳定年説を切る
デブサミ2009で私が話さない(話せない)と決めたことをまつもとさんが話すので興味津々だったのだけれども、たいやき部があるから聞けないなー、と思っていたら息子がたいやき部に行けなくなったので、まつもとさんの話だけ聞いてきた。かっこいい。
話のあとは、自分のセッションの準備をしようとしていたのだけれど、なかなかうまくいかない。困った。
2009-02-08(Sun) [長年日記] [Edit]
■1 RubyKaigi2009のサイトをオープンしました
(この日記は2/11に書いてます)
海外からの問い合わせもいくつかやってくるようになったので、とり急ぎ、現在確定していることを全部書いてオープンしました。デザインは今年ものりおさんです。英語版ページはレオががんばってくれました。
なお、サイトで使っているRubyが1.8系なので、日本語サイトには右上に「アナログ」と表記しています。この日記でも重ねてお知らせしておきたいことは以下3点:
- プレゼンテーション募集(CFP)を開始してます(〆切:3/15)。
- スポンサーも募集しています!!!!。
- 公式タグは rubykaigi2009です。
サイトの情報として足りてないところがまだまだ多いですが、デブサミ2009が終わったらもう少し手を入れていくつもりです。よろしくお願いします。
ちなみにCFPについては、今年は3トラックパラレルでやれるぐらいの数の部屋を押さえちゃってます。応募はお気軽に。プレゼンテーションの内容も、昨年までの「RubyKaigiっぽさ」にこだわる必要はありません。過去3年間のRubyKaigiはどれもセッションの持ち時間が短かかったので、今年は40分とか50分とか、ゆったりと時間を使えるようなセッションも増やしたいです。
ただ、会場の規模に反して動いている実行委員の数が例年並かそれよりちょっと少ない感じ。3トラック平行で回せるだけの現場オペレーションのチームをつくれるのかな……。このままだとKaigiFreaksも人数足りないと思う(去年は2トラック並行してストリーミングするのが精一杯だった)。RubyKaigi手伝いたい!!!と感極まっている方は、実行委員のメンバーと連絡を取ってみてください(あ。公式サイトにチームのページが無い……)。
それから、一部報道で「非公式ながらはてなブックマークのコメントでは『Dave Thomas級の世界的Rubyist』によるキーノートも示唆されている」とありますが、既に公式サイトで発表してますよ?:
- 基調講演: まつもとゆきひろ, 高橋征義
一昨年のRubyKaigi2007のDave Thomasを超えるような基調講演をお願いできるRubyistがいなくて(おっと、ほんとは居るんだけど、断わられてたり、呼ぶべきでないと思ってる)、去年は基調講演はまつもとさんだけになっていたのだけれど、ついに今年は、Dave Thomas級の世界的Rubyist、Masayoshi Takahashiに基調講演をお願いできることになりました(去年はやんわりと断られた)。
どこらへんがWorld-Classかは比較的最近なら、たとえば「Coming From Ruby」(写真の書籍をシアトルまで持参したのが高橋さん)とかFIBURE Bとか「Japanese Rubyists you have not met yet」とか。そういえば「Coming From Ruby」はいつか翻訳をし直したものをInfoQ編集部に送りたいなあ。貴重なdblackの記事なのになあ。
2009-02-12(Thu) [長年日記] [Edit]
つかれたのであとで書く。とりあえずスライド。最後までスライドめくれてよかった。
写真はtakaiのを借りてます。練習不足(というかスライド完成したのが10分前)でリモコンを見すぎてしまいました。情けないです。
よくある質問と答え
- Q:動画はいつ公開されますか?
- A:録画してません。
- Q:予稿とかないの?
- A:ありません。ひとえに私の力不足です。
あわせて読みたい
- 「時を超えたプログラミングの道への道」参考文献:アレグザンダー方面以外 - 角谷HTML化計画 (2009-02-14)
- スライドは何のために公開するか
- "なんでみんなこんなに興奮してるんだかさっぱり分からない...。全く冗長な上に肝心なことはなんとなく図式だけだったりするので、さっぱり伝わらないスライドだと思います"
- はてなブックマーク - kakutaniのブックマーク - devsumi2009 - kakutani
2009-02-13(Fri) [長年日記] [Edit]
(あとで書く)2009/02/18追記
fkino先生最新監訳書籍、『アート・オブ・アジャイル デベロップメント』(TAOAD)のレビューは別途エントリを書くつもりなので、ここではデブサミでのセッションについて。
前半はTAOADを踏まえて、実体験も交えながら(って他人事みたいだけど一緒にやったプロジェクトの話)、XP的に「行儀のよい」テストに対する向きあい方。ここまではちゃんとテストトラック。
で、驚愕の展開の後半。TAOADを媒介に、前半のテストトラック的な内容からシームレスに「飛躍」、一転して話は開発プロセストラックに。ここでもTAOADを下敷にしながらも、fkinoじしんの決意と覚悟を来場者に静かにーーしかし秘めたる熱い思いを込めて語る、心に響くすばらしいスピーチ。「XP (アジャイル) を開発者だけのものにしておくのは、もう終わりにしたい」。
最初は「アジャイルごっこ」から始めたバットマン(ビギンズ!)が、ダークナイトとして再誕した(誕生日に!)瞬間に立ち会えて、しかもそれをfkino専属カメラマンとして撮影できたことを誇りに思う (撮影したときに「これは使うかな?」と思っていた写真が見事に使われていていて嬉しい)。
そして――fkinoは「私たちはあなたがアジャイル開発の『道』を極める手助けをしたい」と来場者に語っていたが、これからぼくら同僚はfkinoがアジャイル開発の『道』を極める手助けをどれだけできるだろうか?
おつかれさまでした!!
(あとで書く)2009/02/15追記
1日目に引き続いて、昼休みにオブジェクト倶楽部のコミュニティブースで『アジャイルな見積りと計画づくり』のサイン会を。一緒に訳したやっとむと、隣ではあわせて書いたい『アート・オブ・アジャイル デベロップメントの監訳者fkinoのサイン会も併催。書籍を販売してもらえるようにSEShopにお願いしたたので(翔泳社なのに!)、売れ残ったらどうしようと思っていたのですが、思っていた以上にたくさんの方々にブースへお越しいただけて嬉しかったです。また、会場販売分も完売(完売です!)できてひと安心。
デブサミ効果か、2/15はAmazonでもほぼ一日中(22時間)総合ランキングで3ケタでした。最高で643位。お買いあげいただいた皆さまありがとうございます。
id:IWAKIRIやid:t-wadaから夜中に突然メールが来て「あしたの13-E-7で書記やってもらえませんか」と頼まれる。この二人に頼まれて断われるわけないだろう。はいよろこんで!! ちょう眠いけど!!!! (id:m_pixyとid:objectclubがんばれ)。
t-wadaと咳さん、太田@mixi(Ken)の当日の事前打ち合わせに参加して「だんだんわかってきた」んだけど、これパネルディスカッションじゃないのな。
t-wadaは最初からパネルなんか意図してなかった。タイトルに偽りありだよ。打ち合わせで「書記って何すんの?」というのを聞いてみたら、つまりこのセッションを「咳に訊け!!」にしたいみたい。なるほど。
咳さんのプレゼンって、素敵なんだけど謎めいているところも多いので、そこをt-wadaがアジャイル実践やチームづくりの立場から、Kenがテスト専門家としての立場から、咳語録をライブで引き出そうというのが狙いだった。つまり、本セッションは正しくはこうだ:
「卓人の部屋 - 第2回 ゲスト:関将俊さん」
ちなみに第1回のゲストはひがやすをさんね(私は参加してないけど)。
ここから、私のミッションは「記録を残す」ではないと理解した。ミッションはt-wadaやkenに続いて来場者が「咳に訊け!!」を実践できるようにすることのサポート。記録を取るのは、質問時に話の流れを遡れるようにするための一時記憶領域を外部化するため。本当にやるべきことは、来場者が質問しやすい雰囲気を(一言も発することなく)つくりだすことだった。ああなるほど。いつもRegional RubyKaigiのIRCでやってるやつね。了解。
といっても現場にIRCはなかったので、howmとQuickSilverのLarge Typeを使って記録しながら会場やt-wadaをイジる。結果として10人以上が質問してくれたので責務は果せたかなと思う。KKDが口火を切ってくれたのも幸いしたと思います。ありがとう。
捺印ナビリティの関係でログは非公開です。参加者しなかった皆さん、残念でした――と思ったけど、純粋な咳さんの発言ぐらいは抜粋してもよいのかしら?
来年のデブサミにも「卓人の部屋」はあるかな?
 打ち合わせ中の咳さんが超かっこよかった
打ち合わせ中の咳さんが超かっこよかった
打ち合せではt-wadaやkenが「あの事(雑談とかで咳さん言っていたようなこと)をこういう切り口で聞きたいんですけど」と逐一(!)確認していくんだけど、咳さんは終始「その質問や問題設定、議論が来場者にとってどんな意味があるか」という観点から、質問の内容やスライドの文言、構成を吟味していた。超かっこいい。
角谷信太郎(友情出演)
t-wadaが直前に表紙のスライドにこうクレジットしてくれた。半分冗談なんだけど、素敵だ。30過ぎて「友情」だぜ? デブサミ2009最後のセッションに、尊敬する方々のセッションにこんな素敵なクレジットで参加できたことを光栄に思います。コンテンツ委員として有終の美を飾れました。ありがとうございます。
それにしても、卓人って名前はよくできてる。Natural Born Agilistだね。技術的卓越の人。t is for testing. t-wadaにこの名前つけたやつ天才 :-)
追記: 大事なの忘れてた。卓人はタクト。どんだけTDD Nativeなんだwww
追記:id:yojikも嫉妬したクオリティの裏側(推測)
そういえば、セッションが終わったあとにid:yojikが(質問ありがとう!)、「『オブジェクトの広場』のインタビューよりも深くて悔しかった」と言っていたけど、それもそのはずっぽい。当日の打ち合わせで咳さんに確認していたセッション当日のスライドは、事前にt-wadaとKenと岩切さんとで作戦を練ってた模様。あれは事前の仕込みの勝利ともいえるんじゃないかな。
仕込みといえば、以前にt-wadaとtakaiとJJUGで鼎談したときも、かなり入念に仕込んだ。あのときはtakai主導だったけど。私はこのときに「書影があればなんとかなる」というのを確信したのだけれど、物理的な書籍の表紙を使った高橋メソッドというスキルをお持ちの方もいるからなあ。
追記: 咳 says...
disclaimer:ログから再構成して若干文脈を補っているので、厳密に同じではありません。お仕事に直接関係しそうなものは削ってます。
「開発の仕方は『XPだったもの』」
「テストの合間にプログラミングしてる」
この2つは有名ですね。
「開発の成果物はソフトウェアとプロセス。プロセスの実行主体としてのチーム」
私が言うとWEB+DB PRESSで8ページかかるところ、咳さんにかかれば1行。
「最初に立場をはっきりさせておきたいんですけど、いわゆる開発の「楽しさ」とかは興味ないから。それが目的になったことはない。でも、プロジェクトがうまくいってることの指標にはなるかも。表情とか顔色で。目が泳いでるとか」
「だって仕事でしょ?」というのは咳フリークにはおなじみの言い回しですね。
(書籍の知識からアジャイル開発は始められるのか?という問いに対して)「本読んだたけでコードなんて書けるようにならないでしょ? それと一緒ですよ。やらないとできるようにならない。そんなのアジャイルに限った話じゃない」
テストでは品質は上がらないですよ。テストはあくまでも品質をあげるきっかけ。品質をあげるのはプログラミングです。これは大昔からそう。
(開発担当とテスト担当とで部門を分かれがちな状況について)「なんか一部の人達には専門性が高いことから『自分たちの領域』みたいな意識があるみたいだけど、あれは責任領域をきめてるんじゃなくて「無責任領域」を決めているだけじゃないの? あれは愚痴なの? 製品の問題なんだったら直接言ってよ。直すから!」
(信頼度成長曲線について)「あんなので信頼度は成長してないよ。ぜんぜん」
(ほんとうのリスクベースのテストについて)「テストしないものを決めてるのかも」
t-wadaが会場には知らない人がいるかもと配慮して「ちなみにRWikiというのは?」と訊いたところ:
「説明していいの? その話、長くなるよww なので、皆さんぼくの本を買って、調べていただきたい!!」
「ストーリーとバグの区別がわからない。顧客の欲しいものといまあるものとが違えば、それは同じもの。バグの種類とかどうでもいいよ。」
「開発はリリースまでにどれだけ理想に近づけるかの挑戦だから」
「どこかに計画があって、それに対するバグを管理してるわけじゃなくて、ストーリーが計画なわけ」
「プロジェクトの中心にストーリーがある、という状態になっているのが大事で、うちの場合はそれがWikiになってる」
「優先順位はどうやって決めるんでしょうか?全員で?」という質問に対して:
「プロダクトオーナーが「じゃあ、何をやめればその機能はできるの?」と言ってくるので「これやめたらできます」って答えてる」
「RWikiは偶然ぼくが作者なので、テストの優先順位を調整する機能が特別に付いてます」
「自動テストができたとすると、そのぶん手が空くんだから、もっと手でさわればいいじゃん」
(テストのやめどきは?と訊かれて)「リリースしにいく係りの人が製品をぜんぶさわってるので、その人に安心して渡せるかどうか」
t-wadaは来場者に「咳さんから『思考停止しないこと』というのがどういうことなのかを感じ取ってください」と伝えていました。
あと、太田さんの「ぼくが実装したら3日ですね。実際3日でした」というのもかっこよかった。どういう文脈だったかは自粛します。
2009-02-14(Sat) [長年日記] [Edit]
■1 「時を超えたプログラミングの道への道」参考文献:アレグザンダー方面以外
(この日記は2/19に書きました)
デブサミ2009で話した「時を超えたプログラミングの道への道」の参考文献をアサマシく紹介しておきます。だいたい登場順。直接言及してないのもあるけど。アレグザンダー方面は、もう少し整理できたら別途紹介したいな。
 『 アジャイルな見積りと計画づくり 〜価値あるソフトウェアを育てる概念と技法〜』
『 アジャイルな見積りと計画づくり 〜価値あるソフトウェアを育てる概念と技法〜』
当日は本書にまつわる話をぜんぜんできませんでした。どこかでリベンジしたい。
![ダークナイト 特別版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Ee-EBYKHL._SL160_.jpg) 『ダークナイト』
『ダークナイト』
ほんとよくできてる。
 『XPエクストリーム・プログラミング入門―変化を受け入れる』
『XPエクストリーム・プログラミング入門―変化を受け入れる』
あわせて買いたい:原著。
 『Head Firstソフトウェア開発 ―頭とからだで覚えるソフトウェア開発の基本』
『Head Firstソフトウェア開発 ―頭とからだで覚えるソフトウェア開発の基本』
あわせて読みたい:「ふつうのシステム開発」。
 『ビューティフルコード』
『ビューティフルコード』
よげんの書。
 『アート・オブ・アジャイル デベロップメント ―組織を成功に導くエクストリームプログラミング』
『アート・オブ・アジャイル デベロップメント ―組織を成功に導くエクストリームプログラミング』
私は今後、本書について何度も何度も言及することになると思う。
 『老子』
『老子』
定番。
 『孔子暗黒伝』
『孔子暗黒伝』
0と1が万物を生む。
 『禅』
『禅』
本書の存在は池上さんに教えてもらった。
 『My Job Went To India オフショア時代のソフトウェア開発者サバイバルガイド』
『My Job Went To India オフショア時代のソフトウェア開発者サバイバルガイド』
ぼくらにとってテクノロジはビジネスであり、ビジネスはテクノロジである。
![マトリックス 特別版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51oRLiE7-%2BL._SL160_.jpg) 『マトリックス』
『マトリックス』
いつもの。
 『ThoughtWorksアンソロジー ―アジャイルとオブジェクト指向によるソフトウェアイノベーション』
『ThoughtWorksアンソロジー ―アジャイルとオブジェクト指向によるソフトウェアイノベーション』
第1章を書いたThoughtWorks創業者Roy Singhamは、時を超えたプログラミングの道に気づいている。
 『Manage It! 現場開発者のための達人式プロジェクトマネジメント』
『Manage It! 現場開発者のための達人式プロジェクトマネジメント』
組織にアジリティを混入させる方法。「全体性」への道。
 『Release It! 本番用ソフトウェア製品の設計とデプロイのために』
『Release It! 本番用ソフトウェア製品の設計とデプロイのために』
正座して18章まで読み抜くべし。18章のために1〜17章が存在する。これもまた「全体性」への道。
![[24時間365日] サーバ/インフラを支える技術 ‾スケーラビリティ、ハイパフォーマンス、省力運用 (WEB+DB PRESS plusシリーズ)(安井 真伸/横川 和哉/ひろせ まさあき/伊藤 直也/田中 慎司/勝見 祐己)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51uK4ACymiL._SL160_.jpg) 『 [24時間365日] サーバ/インフラを支える技術 ~スケーラビリティ、ハイパフォーマンス、省力運用』
『 [24時間365日] サーバ/インフラを支える技術 ~スケーラビリティ、ハイパフォーマンス、省力運用』
そしてこれも「全体性」への手がかり。とてもよい書き下ろしだと思う。
 『銀河ヒッチハイク・ガイド』
『銀河ヒッチハイク・ガイド』
本書のアサマシを検索してたら、DVDが1,500円になっているのに気づいた(ので買った)。本編はともかくオープニングは必見。ぼくは本編も好き。
 世界に一冊しかないXPE2nd
世界に一冊しかないXPE2nd
あの言葉はKentBにもらってから2年以上、色んなところで言及されている。そのわりには自分じしんでは使ったことがなかった。
とはいえ過去に何度か講演や執筆で使おうかと思ったことはあるが、結局はいつも思いとどまっていた。けれど今回のデブサミではやっと自分のなかで踏ん切りがついたのだと思う。胸を張って「みなさんにあげます」と言えてよかった。
Social change starts with you.
2009-02-17(Tue) [長年日記] [Edit]
(この日記は2/27に書きました)
天板だけ交換した。本体は次の使用者のところへと旅立っていった。
贈られたことばのまとめ
私とRubyKaigi、的な様相を呈している。
- 左下: "Write Less software" by David Heinemeier Hansson(DHH) - Ruby on Rails作者。RubyKaigi2006にて。
- 右下: N/A by まつもとゆきひろ(Matz) - Ruby設計者。RubyKaigi2006にて。
- 右上: "Code Ruby Be Happy!" by Dave Thomas - 達人プログラマー。RubyKaigi2007前夜祭にて。
- 左上: "Know Ruby Know Life!" by Rich Kilmer and Chad Fowler - RubyConfなどなどを運営。RubyKaigi2008にて。
まつもとさんからサインをもらうときに一言添えてもらわなかったことだけが心残りだ。
2009-02-18(Wed) [長年日記] [Edit]
(この日記は3/2に書きました)
クリストファー・アレグザンダーの最近の仕事、『The Nature of Order』(秩序の本質)の全4巻をコンプリートした(主にAmazon.co.ukで)。サブタイトルは「An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe」。「建築のわざと森羅万象の本質について」って、エッセイで語るには壮大すぎると思うのだが、筋金入りの中学2年生(厨二歴30年)はそれをやってのけてしまうのであった。
版型もデカくて存在感がすごい。比較のためにKeynote'09のリモコンと並べて撮影してみた。
各巻のタイトルも邪気眼全開。これは読みごたえがありすぎる。
 『The Phenomenon of Life』(The Nature of Order, Book 1)
『The Phenomenon of Life』(The Nature of Order, Book 1)
「生命のあらわれ」。価値記述にとって生命は「度合い」である。テーマは「全体性(全一性)」で、全一性の備える15の特性とか出てくるけど、そんなのはほんの始まりにすぎないっぽい。
 『 The Process of Creating Life』(The Nature of Order, Book 2)
『 The Process of Creating Life』(The Nature of Order, Book 2)
「生命をうみだすプロセス」。パターンやパターンランゲージ以降のアレグザンダーはプロセスを重視していると小耳に挟みました。構造保存変換がフィーチャされているのが本巻。
 『A Vision Of A Living World』(The Nature of Order, Book 3)
『A Vision Of A Living World』(The Nature of Order, Book 3)
「いきいきとした世界のビジョン」。厚い。
 『The Luminous Ground』(The Nature of Order, Book 4)
『The Luminous Ground』(The Nature of Order, Book 4)
「輝ける大地」? すごく……邪気眼です……。
いつかこの中身について語れるようになるべく精進したいと思います。
2009-02-19(Thu) [長年日記] [Edit]
■1 age += 1
世界がいきいきとしますように。
2009-02-20(Fri) [長年日記] [Edit]
■1 「オブジェクト倶楽部2009冬イベント オブラブ冬合宿 ~箱根で湯ったりアジャイル体験~」で合宿しなかった
(この日記は3/2に書きました)
このイベント、正式名称はどれだ。翌日予定が詰まってるので、日帰りで参加。夕方まで「アジャイル開発体験」セッションでコーチ業をしてきた。Web上での感想を見ていると、数は多くないけど参加された皆さんには満足いただけたようで何より。
行きのバスが高速で事故渋滞に巻き込まれてしまって、到着が1時間ぐらい遅れてしまったのだけれど、その間、id:kompiroといろいろ話せてよかった。普段あまりゆっくり話す時間が取れないので、こういう時間は貴重だ。で、そのときに話した内容が「Testing Context(仮)という考え方」というエントリに昇華されている。非常にすばらしい。事故渋滞が生んだ良エントリ。
ブクマコメントを見ると、こういう考え方って実は一般的じゃなかったりして、自分としても新たな発見だった。QuickJUnitに取り込まれるといいなあ。
2009-02-21(Sat) [長年日記] [Edit]
■1 OSC2009 Tokyo/Spring: 「浅草ではRuby 1.9.1を使っています」で前のほうに座ってた
(この日記は3/3に書きました)
事前申し込みでは朝イチなのに「満員」になっていたのでビクビクしながら行ってみると、実際には半分ぐらいしか埋まってなかったという……。
今回のOSCではいつもの「日本Rubyの会」ではなくて地元のローカルグループがRubyのコマを担当ということで、我らがAsakusa.rbの出番ということで、筆頭であるフェロー(笑)さまと世界のko1、あとはなんか知らんけど私。
当日の資料は松田さんのサイトにあるので、そちらを参照。そして、メモラブル・クォート:
“Ruby”は人類の英知の結晶だ。”Ruby”は単にいちプログラミング言語の名前であるのみならず、僕らプログラマーが世の中をもっと良いものにしていく社会的ムーヴメントだ。
Rubyは、プログラミング言語としては必ずしもコンピューターサイエンス的な意味で最高に高度なものではないかも知れないが、どこかの大企業が自社製品を売り込むための思惑が込められているわけでもなければ、誰かの気まぐれな思いつき「だけ」で成り立っているわけでもなく、その代わりに、ユーザーがもっと楽しく、もっと豊かにプログラミングができるようにしたい!というみんなの想いがこれ以上ないぐらい高い密度で凝縮されてできている。
(特に太平洋の向こう側に住んでいる)一部の心ないRailerたちが過去のRubyの一部を切り取った”Ruby 1.8.6”という言語にしがみつこうとしているとかいうような話もあるようだが、おそらく彼らの曇った目にはRubyが”ちょっと仕事を便利にしてくれるプログラミング言語”というぐらいにしか映っていないのだろう。
でも僕らはそうじゃない。今たまたま日本に生まれてプログラマーという人生を選んでRubyという言語に出会ったおかげで、僕らはこの魔法のかかったムーヴメントの真っただ中に身を置くことができる。新しいRubyが毎日作り出されていく奇跡を肌で感じることができる。
さらに、何かしらの形で自分なりのアウトプットを先っちょのほうに投げ込んでみることによって、自分の中の何かがそんな魔法を作り出すエネルギーに変わって世界中を幸せにできたりするかも知れない。この”Ruby”という、世界中を巻き込みつつ未だかつてない規模で進行している「祭り」にリアルタイムで遭遇したというこのチャンスにあなたも参加しないなんてもったいない!
これが、あなたが今すぐにRuby 1.9.1を使い始めるべき最大の理由だ。
Rubyのコマが終わったあとは、須藤社長についていって、2Fの株式会社クリアコードのブースに少しだけお邪魔する。会社そのものを展示していた。株式会社クリアコードではインターンシップを募集しているので、学生の皆さんはチャレンジしてみるといいと思います!!
この後はすぐ、とちぎRuby会議01へ向けて北上。
■2 21世紀Ruby〜とちぎRuby会議01
(あとで書く)(この日記は3/11(水)に書きました)
うまくまとめられないので、ダラダラと。
toRubyの中内さんが実行委員長となって、toRubyの皆さんが運営主体となったとちぎRuby会議01に参加してきた。受付がgreentea(a.k.a tko)さんで、参加者から50円を徴収している様子がシュールだった。
toRubyはRubyKaigi2008での池澤さんによる感極まった行動についてのLTでよく知られているとおり、那須のケント・ベックことid:m_sekiさんが「強い中心」(アレグザンダー的な意味で)になっている。
[電波混信中...]そして、こんかいのとちぎRuby会議01の発表者/講演者もtoRubyのかたちづくる「いきいきとした構造(a living structure)」の「引力」に導かれて、実に多様性に富む素敵なひとびとが東那須野市民会館に総勢30名以上が集まっていた(ちなみにこの人数は「満員」のOSC2009 Tokyo/Sprintのasakusa.rbのセッションへの参加者よりも明らかに多い)。
とりわけ、古参のRubyハッカー――というかオリュンポスの神々が何人も降臨していたことが印象ぶかい。咳さん、greenteaさん、原信一郎さん、gotokenさん、gotoyuzoさん、artonさん、やまだあきらさん。Rubyist-istというかただのミーハー垂涎のデッキ。眼福。こうした古強者のRubyハッカーと、いろんなところで見かける人たちと、「さいきんRubyを始めました」というnewbieとが、toRubyのniceな皆さんのホストする部屋で一緒に半日を過ごすという不思議な時間だった。
そんなとちぎRuby会議01は講演 + いつものtoRuby勉強会 + LTの3部構成と、最後にふりかえり。。
最初の講演の部は、原信一郎さんとごとけんさん。講演の部は、いみじくも咳さんがPerl/Ruby Conferenceを連想すると書いていたように、伝説の「Perl/Ruby Conference 9イヤーズアフター」というか「Perl/Ruby Conference レトロスペクティブ」だったのかもしれないけれど、いわゆる懐古イベントなんかではまったくなくて、20世紀から大活躍している偉大なる先輩Rubyハッカーから、1.9時代の21世紀Rubyを楽しむ僕らへのメッセージだった。乱暴にまとめるなら「Rubyを楽しむこと」そしてそれを「仲間と分かちあうこと」。I'm your toy, your 20th century Ruby.
で、このおふたりのお話を受けて「いつものtoRuby勉強会」。参加者も手を動かす。いまはdRubyを勉強中だそうなので、テキストは当然「幸福の王子本」(まだ初刷買えます?)。これをみんなで写経する(今回咳さんが用意してくれた特別スクリプト)。私はid:yojikと一緒にペアプロして、dRubyを1.9.1で動かしてみたりしていた。曰く「Railsには正直あんまり惹かれないんですけど、Rubyはたのしいっすねえ」と言っていた。メッセージその1。Rubyを楽しむこと。
そしてLTでは「ぼくもRubyでやってみた」「LTに挑戦してみた」といった発表があって、とちぎRuby会議01の全体とよくなじんでいた。美しい流れ。先輩からのメッセージその2。仲間と分かちあうこと。
最後のふりかえりも、その場で感想を共有できたのがよかった。続いての懇親会は、ごはんがおいしかったのはとてもよかったんだけれども、参加メンバーが豪華すぎてオリュンポスの神々とどう絡めばよいのか掴めないまま終了……。きんちょうしどおしだった。帰途は新幹線組で一緒の連れだって帰京。
仙台Ruby会議01からの帰りの新幹線では列を自由にできて、自由席ならぬ自由列だったのだけれども、こちらはさらにその上をいく「自由車」。他に乗客のいないことをいいことに、BGVが酷道動画とか自由にも程がある。
実行委員長の中内さん、運営にたずさわったtoRubyの皆さま、講演された原さん、ごとけんさん、ありがとうございました。近所から遠方から参加されたみなさまお疲れさまでした。toRuby is nice.
関連リンク
- とちぎRuby会議01講演資料リンク集
- 原さんの講演は始めて聞いたのだけれども、資料(原メソッド)もお話もとても素敵だった。ちなみにるびまの原さんへのインタビューは面白すぎるので必読。
- 『極めよRuby道』の記事一覧
- ごとけんさんの。名連載。20世紀Rubyの講演で言及した最適化の話は第8回 スピードアップ。
- 20th Century Ruby
- たしかこんな歌だったと思う。
- タグ「tochigirubykaigi01」を含む新着エントリー - はてなブックマーク
- はてなブックマーク - kakutaniのブックマーク - tochigirubykaigi01 - photos
- とちぎRuby会議01では何人もの方がデジタル一眼レフを持参していて(私は朝、寝坊してあわてて家を出たので忘れた)、やたらと写真が充実している。
2009-02-22(Sun) [長年日記] [Edit]
西船橋での乗り換えの難易度が高すぎる。
息子用にホワイトボードと黒板で両面になってるイーゼルと、以前に試させてもらって割といい感じだったラップトップサポート、こまごましたものを買ってかえった。

![バットマン ビギンズ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/519QZqOPX5L._SL160_.jpg)
 リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大)
リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大) 『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』
『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎)
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎) 実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘)
実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘) The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ)
The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ) アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未)
アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未) インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修)
インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修) アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎)
アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎) JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)
JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)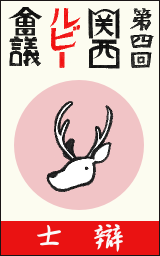



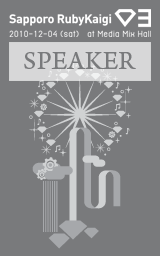






○ うしお [お疲れさんでした。。魂のスライドですね。見ているだけでこっちも高揚してきます。 生で聞きたかったわぁ~。]
○ eto [面白かったです!]
○ snoozer05 [お疲れ様でした!]
○ ISA [お疲れさまでした!! 角谷さんのスピーチと会場の笑い&ドヨメキが聞けず残念ですが、スライドだけでも楽しめました。(翻..]