2011-02-03(Thu) [長年日記] [Edit]
■1 翻訳してる人がいるなら手伝いたいから連絡くださいシリーズ
すでにカミングアウトしているように、いまは"The Agile Samurai"の翻訳作業があったり、他にもあれやこれやそれやがあるので余力がなく、カッとなってガーッとやるんじゃなくて、きちんとした品質のものを届けられるといいなあと思っているものが2つあるから書いとこ(TwitterにpostしたらfavとかRTしてもらえたので、需要あるのかもしれないなあと思って)。
"Agile @ 10" on PragPub—February 2011
by Andy Hunt, Kent Beck, Ron Jeffries, Jon Kern, Ken Schwaber, James Grenning, Arie van Bennekum, Stephen J. Mellor, Ward Cunningham, and Dave Thomas
ものすごい洞察が含まれているというわけでもないんだけど、感慨ぶかい記事。アジャイルマニフェスト10周年(ついに公式日本語訳が!)。
"Growing Object-Oriented Software Guided by Tests"
mockobjects guysが書いたモダンなTDDの書籍。Foreword by Kent Beck(というかKentBシグネチャシリーズ)。
Ward CunninghamのPraise for the Bookがヤバイ。"The authors of this book have lead a revolution in the craft of programming by controlling the environment in which software grows."(強調引用者)
TDDやアジャイル開発にまつわる名言満載なんだよなあ。フルスクラッチで訳す根性が無いんだけど、信頼のおけるチームが翻訳してくれないかしら。訳文レビューとか参加したい!!
きちんとした品質とか書くとエラそうだけど、たとえば「Ruby『出身』」みたいな訳されかたは明らかに残念だと思ってます*1
ああそうだ。無料でWebに公開されてるpragpubはともかくハイエンドな技術書(とかいうと偉そうだけど、「すぐできるJava」的な書籍に比べれば相対的にハイエンドという程度の意味合い)の翻訳出版市場ってなんかもうアレな感じみたいだから、達人出版会でβ版で翻訳しながらフィードバックもらって育てていくとかやればいいんじゃないか。「電子書籍で可能になる、IT専門書翻訳の新しい形態(id:wayaguchi)」みたいなの。価格は原書より高くていいよ。翻訳は付加価値ということで。英語を読める情報強者の皆さんはKindleで原書を読めば安くあがるわけだし。
 The Well-Grounded Rubyist
The Well-Grounded Rubyist
Manning Pubns Co
¥ 3,079
02/05 00:35 追記
「つぶやき」的なtweetに絡むとか大人気ないけど「どういうことなんだろう」って書かれているので少しだけ補足します。
翻訳をしたいという心意気は良いことだと信じているのだけれど、「英語を読める情報強者の皆さん」というのはどういうことなんだろう。情報[強弱]者という "表現" が好きじゃないせいか、原書にあたろうという姿勢が否定されている感じがする… http://t.co/kKJDsI3 2011-02-04 12:17:07 +0900 via Tweet Button
 _sss_
_sss_
_sss_
原著にあたる姿勢を否定してるつもりは毛頭ありません。自分自身が翻訳をきっかけに原著にあたるようになった人間ですし。むしろ、訳書の価格をもっと上げちゃえばいんじゃないのと思ってます。現状は、原著も訳書も大した価格差は無いというか訳書のほうが安かったりすることも多いので。
「高いから仕方ないので頑張って英語で原著を読もう」("情報強者"の皆さん)とか「高いけど英語読めないから仕方ないので翻訳書を買おう」("情報弱者"の皆さん)みたいな感じで、英語ができたほうが書籍代が安く済む、という誘導をしてもいいんじゃないかなあと思ってます。むしろ原著にあたる姿勢を推進したい!!
*1 当時、直したい旨を表明したけど見事Rejectされた。かといって今から直す気力はもうないけど……。
2011-02-04(Fri) [長年日記] [Edit]
■1 RubyKaigi2011の現時点での見通しを書きました
くわしくはRubyKaigi日記のエントリを参照してください。ちょっと文章は取っちらかってますが、情報を出すことを優先しました。ちなみにRubyKaigi関連の公式情報でいちばん速いのはRubyKaigi日記なので、RubyKaigi日記のフィードも購読しておくことをおすすめします。
今月中にはCFPとスポンサーシップ応募フォームは用意したいと思っていますので、心の準備や段取りをボチボチはじめてもらえるといいなあと思っています。
RubyKaigi Advent Calendarについては、たとえば今晩の東京Ruby会議05で声をかけてもらえるとうれしいです。
「最後のRubyKaigi」については@alloyに教えてもらった言い回しが気にいっている:
@kakutani @watson1978 I see, phew :) So it’s more like ‘the last RubyKaigi as we know it’. 2011-01-22 19:49:46 +0900 via Echofon
![]() alloy
alloy
Eloy Durán
the last RubyKaigi(as we know it).
■2 東京Ruby会議05に参加した
私のタイムライン的には完全に、自由でヤケクソに暴れまわっていたRejectTokyoRubyKaigi05(楽しそうだったなあ)の裏番組になっていた東京Ruby会議05に参加してきた。体調あんまりよくないので途中まで。
RubyKaigi2010の会期後半あたりと札幌Ruby会議03あたりで感じられた「Kaigiしましょう」的な雰囲気を抽出しようとしていたのかしらん。平日夜の限られた時間のなかでは健闘していたんじゃないかな。"その場にいないと得られない何かのために集まるという、Ust時代(以降)にあるべきカンファレンスの姿としていいモデルになるんじゃないでしょうか""というtdtdsの見立ては良いな、と思う。東京の地域Ruby会議は開催ごとに特色があって良いね。
オープニングトークの@takahashimの「Rubyのたのしさについて」は高橋さんからの話が半分、会場の参加者とのコール&レスポンスが半分ぐらいで、だんだん場がリラックスしてくる感覚を味わえてよかった。あとarton無双とか。
それにしても「Rubyのよさ」を説明しようとして見事玉砕したRubyコミュニティの巨人の連なりに高橋さんも並んでしまったなあ。これで4人目(このことは札幌Ruby会議03で少し話した:Matz, Dave Thomas, DHH)。だいぶ肉薄していたとは思うのだけれど。Ruby has a quality without a name.
後半はあらかじめいくつか用意されたテーマごとのテーブルに分かれて話し合って、終わったあとにトピックをみんなに伝えて共有するスタイル。
『Using JRuby』がin printになった今日この頃でもJRubyテーブルには誰もいなかった。
私は脱初心者の一歩のテーブルで「絡み力」をつけるために、とにかく絡んでいくしかないみたいなことを話したけど、こういうのって「正解」は無いんだよね。集まりに足を運ぶ以外の一歩についてもうちょっと話したかったけど、時間切れ。地味すぎるけど大事なトピックだと思うので、良い機会があればまた話をしたいな。
2011-02-05(Sat) [長年日記] [Edit]
■1 東京の地域Ruby会議のナンバリングとこの先の予定
東京の地域Ruby会議は他の地域とはちょっと変わっていて「東京で開催する地域Ruby会議」で通し番号を振っています:
東京Ruby会議01
実行委員長 オレ。「Rubyをつくってる人たちの自慢大会」とは違ったカンファレンスのかたちの模索。「Rubyを使ってる人たちの話も聞いてみたいよね」な集い。
TokyuRuby会議01(tokyo02)
実行委員長 @ginkouno(Tokyu.rb)。"カリスマ"誕生。
東京Ruby会議03
実行委員長 @takai。深い技術の話をじっくり聞く「講義」と、同時多発参加型ワークショップ。
TokyuRuby会議02(tokyo04)
実行委員長 @ginkouno(Tokyu.rb)。「室内でやるお花見」という形容詞が生まれた。
東京Ruby会議05
実行委員長 @bash0C7。みんなが話す地域Ruby会議。
「東京Ruby会議」という名前になっている開催は、実行委員長が毎回違ってるのが特徴。これは「自分ならこんな地域Ruby会議を東京でやってみたい」と思ったひとが実行委員長に名乗り出る方式になってるから。だからコンセプトも規模も毎回違う。いまのところ、次の「東京Ruby会議」の開催は未定。ただ、東京の地域Rubyist集団による「東京の地域Ruby会議」の開催は少なくとも2つ決定してる:
大江戸Ruby会議01(tokyo06)
実行委員長オレ(Asakuas.rb)。Askausa.rbのだいたい100回開催を記念して、Asakusa.rbメンバーの生活発表会を深川でやります。
TokyuRuby会議03(tokyo07)
実行委員長 @ginkouno(Tokyu.rb)。tokyu02と同じ、5/29(Go!肉の日)にまたやるらしいよ。待て続報。
次の「東京Ruby会議」を開催することに興味を持ったひとは、日本Rubyの会のWikiの「RegionalRubyKaigi」のページの説明にしたがって、まずはメーリングリストに参加してください。
大江戸Ruby会議01の準備は、ボチボチ進めております。これも正式にいろいろ決まってくればRubyKaigi日記で告知します。
2011-02-15(Tue) [長年日記] [Edit]
■1 tDiary開発者会議20110215でご相談させていただいた
testableがmasterにマージされたけど、今後の作業方針についてtdiary-develへのメールとか日記でうまく説明できる自信がなかったので、いわゆるtDiary開発者チーム殿御中(tdtds,kitaj,hsbt)とお打ち合わせを設定させていただきたく。で、tDiary開発者会議20110215が開催されたので出席してきた。会場提供はエンジニアを積極的に採用しているクックパッドさんでした。お世話になりました。
当日決めたこととかは、togetterにまとめるだけじゃなくて、文書にしておいたほうがよいと思ったのでgithubにWiki Pageは作成しておきました。忘れないうちに更新しておいたほうがよいと思います。誰となく。
testable tDiaryの作業経緯と現状、今後の展望についてのご相談
私のお打ち合わせの資料はslideshareに置いときました。
当日は、Plain Old tDiary を、
Failed Open URL.. http://instagr.am/p/Bn16W/
A JSON text must at least contain two octets!
testable にしてみて、
Failed Open URL.. http://instagr.am/p/Bn1z8/
A JSON text must at least contain two octets!
思ったこととか今後どうしていくのがよさそうか、ということについて40分ぐらいとりとめなく話をしたのを聞いてもらった。うまくまとめきれてない話を聞いてもらえた皆さんに感謝してます。そのあとのやりとりで出た話なんかを踏まえて、もういっぺんやることとその順番を整理するのがいいな、と思った。
今晩のところは大方針と、直近の作業について合意をとりつけられたのでよしとする。次は、もうちょっと手伝ってもらえる人を増やせるように段取りしていかないとなあと思っているところ。
テストの実行の仕方や書き方を整理したらtDiaryのテスティング環境のハンズオンというかチュートリアルというか、そういうのもやりたいなあと思った。
あ、そうだ。おっと大事なことを書き忘れた。
現時点では、みなさんの大事な日記データを運用するわけですからtDiaryはCGI環境で動かすのが安全です!!!
Passengerで動くのはtestableの副産物でしかありません。本番運用にあたっては細ごました問題がたくさん残ってます。
あわせて読みたい
日記だから記録しておこうっと
(すっかり評判が実力を追い越してしまっている今だからこそ現実逃避を兼ねて記録しておく)
- 前提: どこかでtDiaryのことを話すときはつい感極まってしまう(札幌01, 札幌03)
- tDiary開発者チーム殿や、PassionateなtDiary使いの面々の前で話すのはすごく緊張してたし、ナーバスになっていたことにひと晩たってから気づいた。そういえば変な汗をかきどおしだった。
- いまならチャド先輩がRubyKaigi2010のキーノートの冒頭で「ぼくはこの場で話すのが怖かったんだ」みたいなことを言っていた気持ちが心で『理解』できるなあ。スケールはともかくとして(話を聞いてる人の数は数十倍違うわけだけど、私にとっての絶対的な感覚としては同じだ)。
- そういう意味では東京Ruby会議05で絡み力という話をしたんだけれども、10年近い年月をかけて少しずつ少しずつ育まれたオレの絡み力がこれなのであった。みんなはもっと早くさらに遠くにまで絡んでいけると思う。健闘を祈る。
- 自分なりに気がむいたときに少しずつやってて、hsbtが前へ進めていてくれていってたなかで「これどうなんかなー」というぼんやりとしたもやもやみたいなのを、ちょっと勇気をだして(hsbtの支援を仰ぎつつ)思っているところを晒してみたら聞いてもらえた。ほんとうにありがたいことです。
- セコンさんもただ会場番として座ってるだけじゃなくてparallel_specsで実行してみて「これどうなんスか」とか絡んでくれてとてもありがたかった。プロレス的なフリでのブログトップに戻るリンクがついてるWeb日記サービスの話題にオトナな感じで答えてくれたり。そういえばセコンさんは絡み力がかなり高い。
- tDiaryにまつわる会合でtdtdsが前に出るときに空気が変わる感じがするのが好きだ。あの感覚はどこだで感じたことがあるなあ、と思ったら何回か参加してるRubyConfでのMatzのkeynoteが始まる直前の空気が変わる感じにちょっと似てるんだな(あの空気はみんなも一度体験しにいくといいと思う。"やります: RubyConf2011旅費出しますから行ってきて"もあるよ!*1。
- 同じ場所で同じ時間を過ごして同じ空気を吸うということをやらないと生きていけないようなので、インターネッツだけで暮らしていくことは無理っぽい。たとえば #asakusarb もそうなんだけど。言うまでもなくインターネッツが無かったら無かったで暮らしていけなさそうだけど。
- ありがとうございました
*1 日本Rubyの会理事ですキリッ、みたいな立場的には呑気に俺たちのshyouheiがやるらしいからお前ら応募するといいぞ、とか言ってる場合じゃないんだけど
2011-02-16(Wed) [長年日記] [Edit]
■1 とあるプレゼンテーションたちのためにブレインをストーミングしたらゆんゆんしてた
そういえば2011年2月はアジャイルマニフェスト10周年だ。Agile@10とかMike Cohnの"REFLECTIONS ON THE 10 YEARS SINCE THE AGILE MANIFESTO"とか。公式サイトにもいつのまにか日本語訳が載ってる……けど、この訳文でいいのかなあ。特に12 principlesの訳文。だいたい良いとは思うけど(原文)。
引き算で話すことが大事だから、以下を地雷とすればいい。
"a built Whole comprising a soulful composition of timeless forms" -- Jim Coplien
- 質: The Nature of Software, The Nature of Software Development
- 道: The Timeless Way of Programming
- 門: ふつうのシステム開発
- (Lean Architecture)
いまここ
- ぼくらはeXtreme Programmingのかけら
- The Way to The Timeless Way of Programming
- "なんでも聞いて"
DCDアーキテクチャ(Data,Context, KamenRide)
ここ2年間の展開は仮面ライダーを観ればだいたいわかる。
- パターンライダーディケイド: すべてを破壊し、すべてをつなげ!
- パターンライダーW: 俺たちは/僕たちは、二人で一人のプログラマさ, これで決まりだ!
- パターンライダーOOO: 俺が実装する!!!
- 自然と人工, 欲望, "俺は今やれることをやるだけ", コンボ: MVC,UML,DCI
パターン、Wiki、XP
- 私にとっていちばん重なりが強いのはRubyだからこれでいいのだ
- 文化, 部族, パターンの階層
2011-02-18(Fri) [長年日記] [Edit]
■1 Developers Summit 2011で王様のスープをごちそうになった
私にとってのDevelopers Summit、いわゆるデブサミは昨年の2010が最終回だった。「私はDeveloper Summitという名の王様のスープの石」としての役割を終えたから。このエントリでも念のため補足しておくと、「王様のスープ」は中埜博さんの持ちネタで、石のスープの民話のこと。この日記の読者諸賢には『達人プログラマー』の冒頭に出てくることでお馴染のアレ。
で。今年は「おいしいスープをおすそわけしてもらう側」として呑気に参加したかったんだけれど「全力で現状維持」のとっとこ信太郎につき、1日目の午後、会期の25%しかデブサミの「空気」は吸えず*1。とはいえ、この程度の関わりかたでも、滋味に富んだ王様のスープを味わた。私の観測範囲に限っても、今年は去年までよりも素敵な石と、おいしそうな野菜や肉がゴロゴロ入った王様のスープになっていたと思う。ごちそうさまでした。
なかでも個人的なお気に入りは、今年のデブサミでは4年前に自分が腹をくくった場所からはじまったひとつ流れとして同僚である@fkinoが腹をくくってからの話の中間報告をしてくれたこと(これについては次のセクションで補足)。*2
この@fkinoのスライドの最終レビューを初日にオブラブのブースでやったときに、私はあらためて自分がもう1回、腹をくくらねばならないことを見つけた(と思う。続きは上野でやろう)。……だから来年は、とっとこ信太郎じゃなく、王様のスープをおなか一杯いただけるようになっていたいなと思ってる。ただ、ひとつ気になっていることは、デブサミが「10 年計画のプロジェクト」だという理解が正しければ、来年は「Final Developers Summit(as we know it)」なの?
繰り返しになるけれど、ごちそうさまでした。
「17-E-7】デブサミオフィシャルコミュニティから選出のLT大会2011」の冒頭で @kohsei にイジられた件
"デブサミのお母さん"である@kohseiに「コミュニティのLT」で、@t_wada, @papanda, @fkino と一緒にmentionしていただいてたいへん光栄である。えへへ。ただ、どこまでメッセージが伝わったのか、石ころだった身からは少し心配なので、デブサミ2011アドバイザーという立場から2点ほど言っておくか(キリッ
ひとつ目。@fkino を引っ張ってきたのは勤務先のゴリ押しとかアドバイザーが手を回したとかではありません。今年のコンテンツ委員の会議で決めたそうなので、そのへん誤解なきよう。
ふたつ目。去年書いたことをあらためて引用しておく:
今年(引用注:2010)のデブサミでは、自分が登壇したセッション以外でもいくつかのセッションで自分の名前を出されていた。こんなに光栄なことはない。
とはいえ、じっさいにその場に居合せたりするとやっぱり恥ずかしいし「そんなに大層なもんじゃないですよ……」と思ったり言っちゃったりするんだけど(だって本心なんだから仕方ないじゃんね。思想・良心に自由を!)、そうするとそれはそれで「お前がそういうことをいうのは奢りだ」とか「余計に萎縮する」とかお叱りをいただくことも少なくない。でも、今日わかった。私は、石のスープの石だ。石だから、やっぱり大したことはないんだ。でも、楽しそうに石が煮られているのを見て、そこに足りない野菜とか肉をいろんな人たちが持ち寄ってくれるようになったんだ。そういう意味では私はすごい。すごいけど、でも石だからすごくないんだ。そういうことだ。
そういうことなので、私はすごい。すごいけど、でも石だからすごくないんだ。野菜は誰だ。肉は誰だ。ひょっとしたら今年参加した皆さんは何度か耳にしたかもしれないけれど――それは、目黒雅叙園に足を運んで同じ空気を吸った、ustを視聴して同じものを観た、Twitterのタイムラインで流れるテキストを眺めていたみんなだ。次は君の番。It's Your Trun NOW。4年前から言ってたわー。
私は、Developers Summitという名の王様のスープの石だった。
■2 スライドづくりのパターン候補: Drop Your Last 2 Slides
3回以上発見したからこれはパターンだと思うのでアレグザンザー・フォームで書きたいけど眠い。文 章も練れてないけどdumpしとく。
Drop your last 2 slides. Just the final words. It's cleaner.
-- Shintaro Kakutani

(画像はイメージです(そりゃそうだ)。ぼくのプラダのスーツはクリーニング中です)。
あなたのスライドの最後に次の2枚があったらすぐに削ってしまおう:
- ご清聴ありがとうございました
- なにかご質問は?
最後のこの2枚を削ったら、最後に残る1枚のスライドはどんなスライドだろうか? そのスライドは何にするのがいいだろうか?
講演が始まるまでのあいだ、一番長く写しだされているのは(たぶん)表紙のスライドだ。じゃあ、講演が「終わった」あとに一番長く写し出されているスライドは? (たぶん)最後のスライドだ。聴衆が会場から出ていくときに最後に見ることになるスライドが、最後のスライドだ。たぶん。
講演後のやりとりの時間の長さや、あなたのプレゼンスタイル(たとえば1回の講演で80枚以上のスライドを使うようなスタイル)だとしたら、講演時間中を通じてもっとも長い時間、会場に滞留しているスライドになるかもしれない。幸運にも聴衆からの質問があったら、質問者が話してるあいだ、あなたが質問に答えているあいだ、会場に写しだされているのが「最後の1枚」になる。私なりの表現をするならば、プレゼンテーション資料という「背景画像集」のなかで一番長く背負うことになるかもしれない1枚が「最後の1枚」なんだ。
だったらそこには、あなたの講演で、聴衆にいちばん見せたい言葉を載せるのがいい。一番印象的な写真を添えられるなら添えよう。
その写真にはあなた自身の「物語」と結びついた一枚であればなお良い。自分で撮った写真。友達や家族に撮ってもらった写真。理由があって気に入ってる写真。flickrで検索して見つけた写真とか、iStockPhotoやFotoliaで買った写真でもいいけれど、なぜその写真を買ったのか、あなた自身の物語がないと、それは1024x768ピクセルの箇条書きの先頭画像でしかない。
最後の一言は、自分で考えたフレーズでもいいし、引用でもいい。ただし、引用するなら単純にググって見つけた名言じゃないほうがいい。そのことばを引用する理由だけでライトニングトークできそうなぐらいあなたの「物語」と結びついている一言なら最高だ。
削ってしまったスライドに書いてあった、聞いてくれたことへのお礼や質疑の呼びかけなんて、口頭でやればいいんだ――ただし、何事にも例外はある。MatzのRubyConf2010の基調講演の最後の1枚は「Thank you!」だった。でもこの「Thank you!」は、ものすごく重要な「Thank you!」で、こんなに感動的な「Thank you!」って書いてあるスライドはないよね、と @a_matsuda と話していたのだった。 閑話休題。具体例を示します。私の例:
ふつうのシステム開発〜Rubyを活用した受託開発をアジャイルにするためのパターンの紹介

ふう。文体を戻そう。話すと長くなるので解説はナシ。
去年から、デブサミでは発表するのに慣れてない人のスライドづくりのコンサルというかコーチというか、アドバイスをいくつかやっている。以下は今年のクライアントさまの事例をご紹介 :)
nawotoさま: 今そこにあるScrum

スライド構成全体を監修させていただきました。「今そこにあるScrum(Clear and Present Scrum)」というタイトルを考えたのオレオレ。
fkinoさま: これからの「アジャイル」の話をしよう ――今を生き延びるための開発手法とスキル

「最後のスライド」を何にするかはレビューの場では決めてなくて「考えててみたら?」というサジェスチョンまでだったんだけど、いい写真をもってきましたなあ。スライドづくりの観点からは上下の黒い帯と、縁取りのぼかしが無かったら完璧ですね。
私ならこうするかなあ:

なぜこうするかは別のパターンとして話さないといけないんだな。ランゲージすごい。たしか『プレゼンテーションZen』にも載ってた気がするけど。私は岡本太郎の本から学んだ。
デブサミ2010のスライドづくりでの監修実績
ついでに去年お手伝いしたセッションも自己顕示欲全開でご紹介。
- デブサミ2010: 実践Cucumber (@moro)
- 構成を監修しました。スライドづくりはそんなにアドバイスしてないと思う。ソースコードのフォントのことは言ったかも(monospaceを使ったほうがいいよ、とか)。ああそうだ。keynoteで色付きソースコードをつくる簡単なやり方は以外に知られてなかったっぽいからこんど書こう。
- デブサミ2010: SIerのこれからのソフトウェアを創る(@papanda)
- 構成を監修しました。スライドづくりは目にあまるところぐらいしかアドバイスしてないかな。色づかいのコントラストのこととか、行間は0.7、とかそういうのはアドバイスしたと思う。PowerPointはよくわからないです。
というわけで、私でよければスライドづくりの相談をしたいなー、と思われるかたはお気軽にお声かけください。気がむくやつは無料で、そうじゃないやつは応相談。どうぞご用命いただきますようお願いもうしあげます ;-p
2011-02-19追記
kdmsnrにおしえてもらった適切なカットの画像に差し替えた。
2011-02-19(Sat) [長年日記] [Edit]
■1 age +=1
「プログラマ35歳定年説の35歳は0x35歳」と習ったのでプログラマとしてはまだまだヒヨッコです。ハムー。とはいえ、なにやら社会的にも「若手」は35歳までらしい。だから、少なくとも若手じゃなくなっちゃったことは認識しておきたい。念のため補足しておくと人生はつむじ風のパターンなので、若さがとか年齢がとかいった話は個人的には見苦しいので興味ないです。長期的にはぼくらはみんな死んでるわけで。メメント・モリ。
いろんな意味で区切りではあるとは思っているので、ここ10年ほど視界に入ってきたコミュニティとの距離のとり方をまとめようかと、片足がRubyコミュニティで、もういっぽうの片足が「デブサミ的なもの」です、と書きはじめたけどあとは語弊があるだけだからやめとこ。
自分のトークを簡単にふりかえる
代わりに、自分のトークをふりかえっておく。これなら安全。まず、RubyKaigiと札幌Ruby会議で話してきた、"Take the Red Pill"のトークは2年がかりの3部作でひと区切り。
- Take The Red Pill(RubyKaigi2009)
- Welcome to The Desert of The Real(札幌Ruby会議02)
- There is No Spoon:Revisited(RubyKaigi2010, 札幌Ruby会議03)
最後の"There is No Spoon:Revisited"はテキストも書いておきたいと思ってるんだけど、いまだに手が回ってない。
今後しばらくはこれをメインテーマにした話はやらないつもり。ただ、個別トピックのひとつであるRubyKaigiそのものについては今年のRubyKaigiのCFPに出すかどうか迷いちゅう。"the Way to the Timeless Way of RubyKaigi"みたいな感じで。The Final RubyKaigi(as we know it)だしなあ、と思うんだけど。「なぜこれをRubyKaigiで発表するのか」をちゃんと書けたら出したい。
いっぽう、ふつうのシステム開発、The Timeless Way of Programming、The Nature of Software Developmentの流れはまだ区切れるほど練れてないので、今後も引きつづき手を変え品を変え話をつづけていきたい。そのなかの個別トピックであるTDDは、id:t-wadaとは違うニッチを獲得したいと思ってる。
それから、2011年はいわゆる「アウェイ」で話すことをの自覚的なチャレンジとしてる。学ぶことが多いので、胸を借りるつもりで声をかけていただいたらなるべく応えるように調整してます。なのでお声かけはお気軽に。たとえば今年はすでに、日本ファンションポイントユーザーグループの会合で『アジャイルな見積りと計画づくり』の話をするをしました。
2/24(木)に福岡で話す、第6回RubyビジネスセミナーはRubyって書いてあるけど、私の分類ではアウェイかつTDDのニッチを探す旅(これは別途告知エントリを書きます)。
RubyKaigiの運営とかでテンパってきたら忘れそうだけど、もうオッサンだから厚くなったツラの皮でいうと、私が自分の属している業界の一部に与えてしまったプレゼンテーションスタイルの影響については、ちゃんと受けとめてもらえているケースと、いわゆるエピゴーネンになっちゃってるケースがあるので、いくらかは整理して伝えるようにしたほうがいいのかなあ、と思ってる。"Drop Your Last 2 Slides"が書いてみたら(自分にとって)存外フィードバックがあっておもしろかったし。
ボブん家でおたんじょうびディナー
家族3人で外食して祝ってもらえるとかどうしたオレの人生(いろいろありました)。
今月はボブ生誕祭なので、通常5,000円のコースが半額(!)。ボブとは誕生日どころか生年月日が同じだった。人生のステージが違いすぎる(技術翻訳をやっているから仕方ない)。
中華料理だけど錦糸町界隈によくあるマジモンの中華料理店じゃなくて上品な味。食器が素敵。
3人でケーキをWholeでは食べきれないから小さいのにして欲しいってリクエストしたら、小さい型で焼いてくれた。nice.
4sqでチェックインしようと思ったらvenueが無かったのでつくったけど、食べログにはページがあった。っていうかボブん家ブログが(アメブロに)あった。いちど Asakusa.rb あたりで使ってみたい。
おたんじょうびプレゼント
今年はディケイドライバーとWドライバーとオーズドライバーにガイアメモリ12本とコアメダルを9種類もらいました。豪華。予約特典でオリジナルガイアメモリ「おとうさんめもり」がついてきた。ありがとう。
■2 大事なお知らせをひとつ忘れていました
2011-02-20(Sun) [長年日記] [Edit]
■1 『ゾンビランド』
けっきょく劇場にはいけなかったのが悔やまれる。これはスクリーンで観たかった……。 イマドキっぽい編集の全速力ダッシュ系のゾンビ。清く正しい(ちょっとだけメタな*1)エンターテイメント。好きだ。
ジェシー・アイゼンバーグ(『ソーシャル・ネットワーク』でザッカーバーグ役だった人ね)が、 ゾンビランドになって良かったことに「もうFaceBook更新しなくていい」とか言ってたのはさすがにフイタ。
ウディ・ハレルソンは抜群の安定感。
ビル・マーレイのああいう絡みかたって素敵だなあ。なんなのあれ。ああいう大人になりたい。『ダージリン急行』でも走ってたけど、ああいうのが彼の後進への接しかたなのかな。ゴーストバスターズといえば『僕らのミライへ逆回転』を思いだしたけど、これはまた別の話だな(そういえば『グリーン・ホーネット』はどうだったんだろう)。
 ダージリン急行 [DVD]
ダージリン急行 [DVD]
20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン
¥ 1,000
 僕らのミライへ逆回転 プレミアム・エディション [DVD]
僕らのミライへ逆回転 プレミアム・エディション [DVD]
ジェネオン エンタテインメント
¥ 2,450
*1 本作はゾンビを「ゾンビ」と呼ぶカテゴリの作品でもある
2011-02-23(Wed) [長年日記] [Edit]
■1 2/24(木)の午後に福岡でRailsのテスティング環境の話をします
もう明日なんですけど:
というわけで福岡に行きます(というかさっき着いた)。席にはまだ余裕があるみたいなので、木曜日の午後3時から2時間ぐらい、福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センターに来れそうな方は是非ぜひ。
- 1. Rubyコミュニティでテストをする文化が重視されている理由
- 2. 現時点でのRuby on Railsのテスティング環境の全体像
あたりを中心にお話したいと思っています。『WEB+DB PRESS』Vol.61の特集2「Rails3 テスト最前線」(@:ursm,@:hsbt,@:kenchanが書きました)の内容を補完できるような視点を提供できたらいいなあと思ってます。
いちおう昨晩、Asakusa.rbメンバーに聞いてもらったら、それなりに興味をもってもらえたので悪くないんじゃないかな(@:a_matsudaや@:takahashim,@:t_wadaには具体的なアドバイスももらえました。thanks!)。がんばって準備を間に合せたい。皆さまとお会いできることを楽しみにしています。
2011-02-24(Thu) [長年日記] [Edit]
■1 第6回 Rubyビジネスセミナー:「ふつうのRuby on Railsのテスティング環境」
昨日告知したやつを無事終えました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。一方的に講演するだけじゃなくて、質問をたくさんしていただけて救われました。メイシーの中の人たち :)と会えたのがよかった。チャリで来てた。いいな。オレも大江戸Ruby会議01はチャリで行こう。
当日の背景画像集です:
話す内容はもっと削らないといけなかった。引き続き精進を重ねていきたい。ブレインストーミングにお付き合いいただいた、@:haru01,Asakusa.rbメンバーの皆さんありがとうございました。
以下、講演でアナウンスしたことこちらでももう一度:
TDD Boot Camp福岡
ところで、3/19,3/20のTDD Boot Camp福岡は(男性の)宿泊枠はなくなったけど、参加枠はまだあるので是非ぜひとt-wadaに言われたので宣伝してみたけど、これ通えるのか??
Testing w/ Rails using Rspec in Japanese (#trrja)
この発表のcall for actionを考えていて「そういえばRSpecをつかってRailsのテストをすることについて、日本語で誰となく相談できるようなオンラインの場ってないなあ」と思ったのでこれを機会につくるだけつくってみたのが、Testing w/ Rails using Rspec in Japanese(さしあたってはgithubのWikiを使うところから始めてみようかなと)。連絡とかやりとりにはfacebookのグループを用意してみた。うまくいくかどうかわからんけど、まずはやってみよう。
RubyKaigi 2011 ではスポンサーと発表を募集しています
- RubyKaigi2011 スポンサー募集
- RubyKaigi2011 発表募集 (締切:3/20(日))
 WEB+DB PRESS Vol.61
WEB+DB PRESS Vol.61
技術評論社
¥ 1,554
 禅とオートバイ修理技術〈上〉 (ハヤカワ文庫NF)
禅とオートバイ修理技術〈上〉 (ハヤカワ文庫NF)
早川書房
¥ 798
 禅とオートバイ修理技術〈下〉 (ハヤカワ文庫NF)
禅とオートバイ修理技術〈下〉 (ハヤカワ文庫NF)
早川書房
¥ 798
2011-02-25(Fri) [長年日記] [Edit]
■1 2/25(金)の夜に名古屋アジャイル勉強会第30回「『アジャイルな見積りと計画づくり』のエッセンス」に参加するよ
って今晩だけど。詳細は名古屋アジャイル勉強会の告知を参照してください。基本情報だけコピペします。興味があって間に合いそうなら是非お越しください(リンク先によれば、これまでの読書会に参加してなくても大丈夫だそうです)。
■開催日時 2011年2月25日(金) 19:00-21:00 ■場所 名古屋市女性会館 第1研修室 地下鉄名城線「東別院」下車1番出口より東へ徒歩3分 ■参加定員 25名(先着順) ■参加費 200円(会場費および用具代として)
とちぎRuby会議03の4倍のAdmissionが必要な勉強会だ。こういうときAEPの訳書をKindleに入れてもっていけるといいんだけど。名古屋アジャイルではかなり丁寧に『アジャイルな見積りと計画づくり』の読書会をやっていたようなので、御礼を伝えたいのと、皆さんがどんなことを考えたのかを聞きにいけるので、楽しみにしています。
2011-02-26(Sat) [長年日記] [Edit]
■1 名古屋Ruby会議02に行った、ような
前日に名古屋入りするために新幹線に乗ったときから、なんか頭がボーlっとしてて『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』(22)を読みすすめるのも必死、みたいな感じだったのだけれど、名古屋Ruby会議02の当日は完全にダメな感じ。座ってるがせいいっぱい。なので具体的な感想とかははてブのnagoyarubykaigi02タグだのみ。
個人的は名古屋Ruby会議01が、ちょっと枠組み先行な感じに見えたので心配していたのだけれど、今回参加したら、地元の人たちが、地域を縁にした周囲とのつながりを活かした Kaigi になっていたのでとても、とても良かった。名古屋の(わりと近所の)Hamamatsu.rbというのもできていたようで、これからの東海地方の活動が楽しみにな感じ。運営チームと当日スタッフのみなさん、お疲れさまでした&ありがとうございました。
しかしまあ「名古屋のRubyコミュニティが心配だから!」とかいってとちぎRuby会議03じゃなくてこっちに来たのに、逆にみんなから「大丈夫ですか?」と心配されてなんというかトホホ。
懇親会も参加予定だったんだけど、間の時間にちょっとホテルに戻って休憩しようと思ったら、そのまま気絶してて起きたら23:30だったという……。そのままもう一度寝たら翌朝はずいぶんと良くなったので、スーパーヒーロータイムを観て、山本屋で味噌煮込みうどんを食べて、名古屋駅でうなぎパイなどのお土産を買って帰京(これは名古屋駅なのにお土産屋でうなぎパイを売るほうが悪い)。


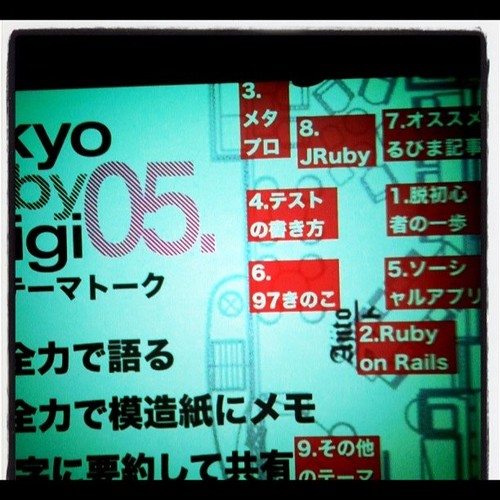
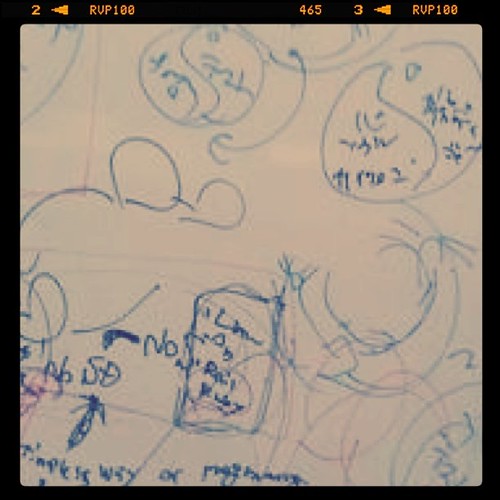



![ゾンビランド [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61yN09qLLHL._SL160_.jpg)




 リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大)
リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大) 『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』
『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎)
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎) 実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘)
実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘) The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ)
The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ) アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未)
アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未) アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎)
アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎) インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修)
インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修) アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎)
アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎) JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)
JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)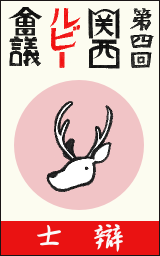



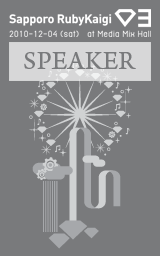






Before...
○ かくたに [タイトルは別にあれでもいいんですけど、なんか訳文が全体的に生硬で残念だなあと。]
○ かわにし ["Growing Object-Oriented Software Guided by Tests" 自分も手伝いた..]
○ かくたに [じゃあまずは、そもそも翻訳してる人をさがしだすところから手伝ってください :< ]
○ eitoball [Agile@10のほうをやってます]
○ かくたに [連絡ktkr!]