2008-10-01(Wed) [長年日記] [Edit]
■1 「ファンクション倶楽部2008秋イベント〜 lambda the world 〜」を開催します
オブジェクト倶楽部のメルマガですでに告知していますが、10/30(木)にイベントを開催します。場所は、田町にあるLisperの聖地(ということになっている)居酒屋、 (car (cdr ("y" "a"))) です。オブジェクト倶楽部に潜入している「諜報部員」(2008/03/11 08:36:18 PDTを参照)3名が、SchemeとかHaskellとかの話をする予定です。いま参加者リストをみたら羽生田"すからてちん"栄一のはてなIDがありました。会場の都合で参加人数に限りがありますから、お申し込みはお早めに。居酒屋で開催するので費用もかかりますから。あと、申し込みサイトはATNDを使っているので、参加登録にはOpenIDが必要ですから。
ファンクション倶楽部2008秋イベント ~lambda the world~
- 開催日時: 2008年10月30日(木) 19:00~21:00
- 場所: (car (cdr '("y" "a"))) (かく田や;JR田町駅徒歩10分)
- ライトニングトークスへの申込み : http://tinyurl.com/oblove2008autumnlt
- 主催:オブジェクト倶楽部
- 定員: 30名
- 参加費用: 4,000円(ワリカンにご協力ください)
- 参加登録: http://atnd.org/events/99 (OpenIDが必要です)
- プログラム:近日公開予定です
ustは、やれたらやります(たぶん私が担当……ちゃんとやれるかな)。
2008-10-03(Fri) [長年日記] [Edit]
■1 札幌Ruby会議01に道外から参加する人たち用のMLをつくった
のでした。qwik.jpで。
興味のある方は、メールで参加してください。
to: sappororubykaigi01tour _at_ qwik _dot_ jp cc: shintaro _at_ kakutani _dot_ com subject: 札幌Ruby会議01参加したい! 本文: 自己紹介など
'_at_'とか'_dot_'とかはSPAM避けのつもりなので、置換してください。
札幌Ruby会議01はメイントークだけでなくLTも豪華すぎる布陣のなか、私が最後にしゃべるというこれは、試練だな。
2008-10-04(Sat) [長年日記] [Edit]
■1 「 Rubyist Magazine - Rubyist Magazine 0024 号」がリリースされてしまった
またRSpec連載の原稿を落としました!!! 札幌Ruby会議01で「Working Effectively with Legacy tDiary Code using Cucumber and RSpec」というタイトルで話す予定なのでそれで埋め合わせとさせてください……。
以下、ダラダラと。
記事を投稿しまくっているid:kwatchが「るびまはフェードアウトするみたいだ」と釣り糸をたらしているけれども、何をすればいいんだろうな。自分としては、いちおう記事を書くのがいいのかな、と思ってちょっと頑張ってみたのだけれども、力及ばず……というかんじ。桑田さんは記事を3本寄稿してさらに札幌Ruby会議01のLTにも登壇されます。私なんかとは格が違うのだよ!!
ささださんのふりかえりは、何事もささださんは自分の設定目標が高すぎるようにも思うので、どこまで言葉どおりに受け止めればいいのかわからない。具体的な問題が見えてこないなあ。どこから手をつければいいのか。というか手をつければいいものなのか。初心は「やりたいからやる」のはずだったわけだし。
参考までに、海の向こうでは(って、lulu.comでPDFを買えるけど)「the Rubyist」なんてのが出てる(PDFなら$3。紙は$8?)。実はPDFを買うだけ買って読んでない。
それから「ぜひとも各地で行われている勉強会やリジェクト会議の発表などを記事として残して欲しい」という声は、tanabeさんの東京Ruby会議01レポートがその試みのはじまりのつもり(snoozer-05の提案)。明示されてないけど、このコーナーは「RegionalRubyKaigiレポート(01)」となっている。つまり、連載(の予定)。だから今後もRegional RubyKaigiは、各開催のレポート記事を寄稿してもらおうと思ってます。このへんのRegional RubyKaigi開催の流れは、いまは個別対応になっちゃってるけど、いずれ文書にまとめる予定……。
あとはRubyKaigiでゴルフコンペなんて企画をやれたのもshinhさんの連載のおかげだもんな。
Rubyにまつわる文書がらみでは、私はるりまは何もお手伝いできていない。
2008-10-05(Sun) [長年日記] [Edit]
■1 github_badge プラグインをつくった
みんな大好きDr.Nic(求職中)がつくったGitHub Badgeがカッコイイので、tDiaryのプラグインを書いてcoderepos.orgのtDiary contribに置きました。kakutani.comにも貼ってます。こんな感じ:

使い方の基本は:
{{github_badge('kakutani')}}
です。github.comでのユーザ名を指定します。いちおう各種オプションも指定できるけど、インターフェイスがかなりひどいので、いつか設定画面を用意したい。
2008-10-10(Fri) [長年日記] [Edit]
■1  『 The Phenomenon of Life: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe (The Nature of Order, Book 1』
『 The Phenomenon of Life: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe (The Nature of Order, Book 1』
発注してしまった。おれはもうだめかもしれない。宇宙、人生、すべての質問。
2008-10-11(Sat) [長年日記] [Edit]
■1  WEwLC読書会#5に参加してきた
WEwLC読書会#5に参加してきた
読書会の存在は以前から知っていたのだけれども、初参加。こんどの(ってもう再来週か。やばい)札幌Ruby会議01で「Working Effectively with Legacy tDiary Code using Cucumber and RSpec」というタイトルでしゃべることもあって読み返していた。というか、実は『Working Effectively with Legacy Code』はほぼ4年前に紹介して以来、導入とカタログ以外(つまりPartII)にはきちんと目を通していなかったという。
読んでると自分の読み方に自信がなくなってきたので、読書会の皆さんはどんな風に読んでるのか確認してみたくて参戦してきた。皆さん発表内容も資料もよくまとまってるし、楽しくアレンジしてあったりして非常の有意義な時間を過ごせた。初参加のくせにベラベラしゃべりすぎたけれども、自分の読み方や考えの方向が合っていることを検証したかったのであまり自重しなかった。ちなみに、私のなかではWEwLCの第23章を書いたのはid:t-wadaということになってる。
運営幹事のせとあずささん、会場を提供いただいたサイボウズ・ラボさん、発表された皆さんありがとうございました。そういえばこの読書会もプラクティス:「3時のおやつ」を実践していた(JavaEE勉強会から輸入?)。あれは良いプラクティスだなあ。なごむ。
心残りなのは、この種の読書会は本を読んでるのは壮大な前座で、本編が懇親会なのに、参加できなかったこと。フォースの調和と締め切りには勝てないので仕方ないのですが。また機会があったらよろしくお願いします。
次回は11/8みたいだけれども、この日はRubyConf2008なので参加できないなあ。ものすごい勢いでザクザク進んでいるので本書の読書会としては次回が最終回らしい。第24章は短いけどとてもとても素晴しい章なので、ソフトウェア開発の現場で泥ではなく星を見ていたいような暑苦しい思いを胸にかかえた人が担当するといいと思う。
2008-10-13(Mon) [長年日記] [Edit]
■1  『Manage It! 現場開発者のための達人式プロジェクトマネジメント』
『Manage It! 現場開発者のための達人式プロジェクトマネジメント』
『Ship It!』に続いてオーム社から(オーム社から!)出ます。達人プログラマーの本棚シリーズ。Do It!シリーズで残ってるのは『Release It!』か。
すでにkdmsnrやbeakmarkといったレビュワーな方々による紹介や、Agile2008のExprience Reportでプロデュースしてもらって著者本人とも面識のあるfkinoのwktk感が既に更新されているので、そちらを参考に。
私は今はちょっとまだ読めないので(すみません)、原書をざーっと見たときのおぼろげな記憶とともに本書と関係あるような、ないようなことを言っておこう。
いまたぶんアジャイル開発の業界シーンを把握するならInfoQのアジャイルカテゴリが非常によくて、彼らは本気でやろうとしているんだなあ、という空気を読みとれる。(その一部を翻訳したり、日本語の独自記事があったりしているのが、InfoQの日本語版のアジャイルカテゴリ)。で、本書もそういう文脈に位置づけられる一冊だと思う。
本書のポジションは:
- 『リーン開発の本質』に比べると現場寄り
- 『アジャイルプラクティス』に比べるとマネージャ寄り
- 『XPE 2nd』に比べると「現実」を認めている(Social Change度は低め)
かなあ。特に最後のポジションは重要じゃないかしら。プロジェクトマネージャ向けだね――って、だから『Manage It!』なのか。うまいこと名前つけたな。
ところでいま、Pragmatic Bookshelfで5周年祭が開催されていて、過去5年間に購入した冊数に応じて最大60%ディスカウント実施中らしい。私は35%ディスカウントでした。何冊買えば60%ディスカウントなんだろう。私の購入履歴は19冊だった。
2008-10-17(Fri) [長年日記] [Edit]
■1 JJUG クロスコミュニティカンファレンスでしゃべってきた
今回はいつにもまして色々な人たちのお世話になったので、最初に大事なことを。何よりも、私たちのセッションに参加していてくれた皆さま、ありがとうございます。そして、そもそも私の「java-jaだったら『JavaからRubyへ』の話してもいいよ」という言葉を真に受けて声をかけてくれたid:Yoshioriと、今回の登壇にあたって色々と場をとりなしてくれたid:higayasuoに感謝を。それから、私(たち)からのSOSに応えてくれたtakaiにも謝辞を。それからそれから、連日のタワーズ・クエスト通いに快く応じてくれたペアプロ相手のid:t-wadaにお疲れさまと伝えたい。そして最後だけれも一番重要な人たちに。直前にイッパイイッパイになった私から仕事を押しつけられてしまったチームのみんなと、妻と息子にありがとう。
以下は自分が登壇したり手伝ったりしたセッションについて:
 『JavaからRubyへ』・アンド・ナウ
『JavaからRubyへ』・アンド・ナウ
RubyKaigiに続く「アンド・ナウ」シリーズ第2弾。takaiのナビゲートで私がしゃべって、id:t-wadaに補足してもらうという構図をつくってもらいました。主なトピックは以下3つ。
- 「JavaからRubyへ」:どんな本で、なんで翻訳して、どうしてアオるのをやめたのか
- 「EJBからRailsへ」:Bruce Tateの史的唯物論の帰結としてのRailsは物事の一面しか捉えていないんじゃないの
- 「JavaとRuby」:World-Class OO厨としてのDHH。「実装してみたシリーズ」としてのRails。どちらが、ではなくて「どちらも」なんじゃないかなあ、という話
「Java vs. Ruby」という図式よりも、その背後を深く流れる「ソフトウェアのOOPSLA派(OOPSLA学派)の水脈を知ってもらいたいなあ、というのが極東の登壇したOO厨たちの願いだったのだけれども、どれだけ届いたのか壇上からはよくわからなかった。ただ私たち自身はこの話をできてとても満足だった。当日のプレゼン資料はtakaiが用意してくれました。takai++
 YET ANOTHER GREEN IT
YET ANOTHER GREEN IT
タイトルは出オチ。TDDとペアプロでグリーンITが持続可能なソフトウェア開発ですよ! というわけでid:t-wadaと久しぶりにペアプロした。
ふつうペアプロのときは1コマ90〜120分で1セッションなので、今回の45分はかなりキビシかった。それなりに仕込みを入れても、やっぱりなかなか本番はうまくいかないものだなあ。もしも部屋にいる皆さんに実際のペアプロの空気や間合いを感じてもらえたとしたら成功。壇上のふたりは、緊張しながらも楽しんでおりました。
それから、当日のネタとして苦し紛れに選んだRESTful世界時計が、自分たちの予想を遥かに上回るペアプロやTDDの進め方のうえでの気づきを得られたのがよかった。説明の仕方をもっと整理すれば、ふつうに実践的なTDDの進め方の作戦のネタとしても悪くない気がする(ボウリングよりいいかも)。それにしてもid:t-wadaにはほんとうにお疲れさまといいたい。私も疲れた。
いちおうスライドを置いときます:
持続可能なソフトウェア開発についてはそのまんなのタイトルの書籍があるので、そちらもどうぞ。
java-jaのライトニングトークス
みんな若々しくて元気でいいなあ、とオッサン臭い感想を抱いた。私もLT出身だからか、なんか甘酸っぱい思いにつつまれた。java-jaの前途に幸あれかし。
なんか成り行きでタイムキーパーをやることになったので、kaigi_timeKeeperを投入してjava-jaに鈴音ミホを轟かせてきた。ドラ娘ことid:objectclubもお疲れさまでした。
追記:あわせて読みたい
あと、大事なの貼るの忘れてた:
会場で「読んでない人」と訊いたら結構な数の手が挙がってびっくりした。コミュニティ活動に出かけていくのもいいけど、この本はイベントn回ぶんの価値があると思います。
2008-10-18(Sat) [長年日記] [Edit]
■2  『 The Phenomenon of Life: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe (The Nature of Order, Book 1』
『 The Phenomenon of Life: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe (The Nature of Order, Book 1』
発送予定日11/5〜11/24だったくせに何故か今日とどいた!! こういうときだけ早く送ってくるなよAmazon!!! 予定がいろいろ狂うだろ!!!
2008-10-19(Sun) [長年日記] [Edit]
■1  『アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣』の第5刷見本誌が届いた
『アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣』の第5刷見本誌が届いた
おかげさまで、じわじわ売れているようで、とうとう第5刷に突入しました。読者の皆さまのおかげです。装丁は原著者のひとりであるVenkatにも気に入ってもらえたようで嬉しいです。増刷状況や正誤表はサポートページで確認できます。ネットでの反応ははてブのagile_practiceタグにクリップしています。
ブログを読んでいると、ときどき『アジャイルプラクティス』の読書会を開催している人たちがいるようなのだけれども、お邪魔でなければ声をかけてくれれば、可能な限り都合をつけて参上つかまつります。本書を読んだ人たちがどういうことを考えているのか、いち監訳者として興味があります。
これまでの実績としては、あまのりょーさんの勤務先にfkinoとふたりで行きました(当時のfkinoの日記)。今後の予定としては、まずid:papanda0806の勤務先にこれまたfkinoと行くことが確定しています。いまのところ、XPJUG界隈のいわゆる「町内会」つながりでしか呼ばれてませんが、いつか「本邦アジャイル界」みたいな町内じゃないところから呼ばれてみたいなあ、と思ってます :-)
ああそうだ。あわてて補足しておくと「5刷」とか書くと「印税いっぱいもらいやがって」みたいに思われるかもしれないので、yomoyomo先生の金言を引用しておく:
書き下ろしとは違うのだよ、書き下ろしとは!! しかもこっちは監訳かつ2人がかりだから!! みんなもっと買って!!
2008-10-25(Sat) [長年日記] [Edit]
■1 札幌Ruby会議01で発表してきました
とりいそぎ、資料だけ置いときます。Rackの使い方がかなりアヤシイので、そこは参考にしないでください ><
CucumberとRRは面白いので皆さん試すといいと思う。あと今日は紹介できなかったけど、factory_girlもオススメ。testable_tdiaryはとりあえずpushしただけなので、もうちょっと整理します。今回はコードと資料を両方準備するのが大変だということを学んだ。
いきいきとしたレガシーコードとの暮らし
2008/10/28追記:全セッションの動画が公開されました。早い!!
一覧するならTechTalk.jpが便利かな。ニコニコ動画のアカウントをお持ちでない方は、RubyKaigi日記でご覧ください。
前編
後編
○ kou [RRのAPIはいいですね。英語じゃなくてRuby言語らしいAPIなので。 (個人的にはreturnsはなくてブロック..]
○ かくたに [>kou returnsをつかうのは、コストのかかる値をmock/stubの戻り値にするときなのでハフマンコーディン..]
○ kou [なるほど。 ところで、コストのかかる値を戻り値にすることはわりとあることなのでしょうか? イメージというか経験的とい..]
○ かくたに [たぶんそうなんだろうなあ、という以上のことはなくて、実は具体的な使いみちは私も思いつかないです。そういうケースに遭遇..]
○ arton [ありがとうございます。注文しました。]
2008-10-26(Sun) [長年日記] [Edit]
■1 わたしとRuby札幌
確か始まりは、RubyKaigi2007の当日スタッフへの応募メールだったと思う。札幌から2人の若者が応募してきた。「こういう人たちは放っといても来そうだし、チケット買えなかったら可哀想だから、ついでに手伝ってもらおう」。そんな軽い気持ちで私は彼らに当日スタッフをお願いした。彼らが友人同士だということも知らなかった。
会場準備の日にやってきた彼らは、一人は誠実そうな青年で、もう一人はベイビーフェイスのハンサムな若者だった。若いほうのハンサム・ガイは東京での宿はインターネット喫茶だという。ネカフェ難民じゃねえか……。
なんだか異様によく働くふたりは、(たしかid:ogijunのおかげで)「伝説の」Dave Thomasの基調講演を目の当たりにできたのだったと思う。「沢山の人々がこのコミュニティにやってくる。彼らを迎え入れて、我々のやりかたを見せてあげるんだ。『Ruby道』を」――私のようなRuby厨の心臓を貫いたDaveのメッセージは、間違いなく彼らの心臓も射貫いたのだろう。「ぼくらはぼくらの街の札幌で、Rubyの楽しさを伝えたいんです」たしか、snoozer05というidのほうの青年がそんなことを言い残して、彼らは北の大地へと帰っていった。「北海道でRuby道とか……誰がうまいこと言えと……」そんな軽口を叩いたかもしれない。
彼らが札幌に戻ってしばらくすると、Ustream.tvがローンチした。いち早くUstream.tvに注目した彼らは、自分たちの勉強会を配信し始め、ものすごい勢いで道外との距離を縮めはじめた。彼らの配信活動の積み重ねは、とうとう太平洋の真ん中に居ながらにして「札幌に行ってきた」と言わしめるほどになった。
彼らが配信している様子などを通じて、どうやら「Ruby札幌」にはRubyKaigi2007に来た彼ら以外にも仲間がいるらしいことが私にはわかった。そして、年が明けて2008年2月。JPUGとの合同イベントに呼ばれたときに、山と刺身の積まれた舟盛りを前にしながら、snoozer05が言った。「今回はかくたにさんに来てもらえたので、次は咳さんとartonさんを札幌に呼びたいんです」。また、こうも言っていたと思う。「僕らが体験したRubyKaigiを、札幌のみんなにも体験してもらいたいんです」と。
かくして、時は流れて――といってもほんの8ヶ月程度なのだが――10月25日。快晴だが少し肌寒い土曜日。北海道庁のほど近く、北大植物園の向かいの建物にartonさんと咳さんがいた。
札幌Ruby会議01。参加していた人数は全部で70名ほどだったろうか。しかし、Ustream.tvのFlashの画面の向こうにはさらに70名ほどの人たちが居たようだ。RubyKaigi2007にやってきて、札幌でRubyKaigiをやりたい、と言っていた彼らのつくりあげたRegional RubyKaigiの雰囲気は、驚くほど最初のRubyKaigi、つまり2006年にお台場で開催したRubyKaigi2006の空気に似ていた。この共通点は何も「どちらもtDiaryの発表があったから」ということだけに限らない。
多すぎない人数。あたたかく迎えられているというリラックスした雰囲気と、そこに同居する緊張感。初々しさ。わくわくする感じ。発表者それぞれが持ち味を発揮しながら、聴衆も段々とそれに応えられるようになっていく。徐々に熱くなっていく会場の空気。なんだか、とても懐かしかった。慌ててつけくわえておくと、自分がDHHだというつもりは毛頭ない。
たしかに、札幌Ruby会議01は「お客さん講演がメインで、Ruby会議札幌出張版という感じだった」かもしれない。でも今回ばかりはそれが「Ruby札幌」という旗印に集まっていた彼らの目指したところだったんだと思う。「発表者と聴衆とスタッフというようにはっきり別れて...壁をつくって」でもやりたかったことなのだと思う。「札幌でRubyKaigiを実装する」ということがいまのRuby札幌に必要なことだったのだと思う。そして、その試みは成功したと思う。
しかし、繰り返しになるが、やはりそれは「札幌Ruby会議」ではなかったと思う。だが、これが最後ではない。札幌Ruby会議01のクロージングでは、東京でも明言していない(と思う)「札幌Ruby会議02」開催宣言がsnoozer05から出された。思うに、次こそが札幌Ruby会議が札幌Ruby会議になるべき時だ。「札幌じゃなきゃいけない意味とはなんなのか」、それが問われる。そしておそらくそれは今回よりも難しい問題設定になるだろう。
だが、希望はある。札幌Ruby会議01に参加された皆さんは、日本Rubyの会会長こと高橋征義さんのライトニングトークは聞かれただろうか。今回の高橋さんのトークは神がかっていた。個人的には「日本Rubyの会設立について」以来の衝撃を受けた(後日アップロードされるらしいニコニコ動画の録画であの空気は伝わるのだろうか)。「札幌という場所でRubyとかかわること」。今回の札幌Ruby会議01の基調講演は、間違いなく高橋さんのトークだったと思う。高橋さんの真摯なメッセージが、札幌の皆さんに一人でも多く伝わることを願ってやまない。
高橋さん御本人は「結局肝心なことは何も語っていないような気もします」と書いているが、それでも、Webキャリアのインタビュー(前編)(後編)はあわせて読みたい。
……だいぶ話がそれてしまったけれど、乱暴にまとめると、今回の札幌Ruby会議01は、Ruby札幌にとって一つの到達点だったと思うし、それに相応しい素晴しいイベントだったと思う。つつがなく全プログラムを終了することができてよかったです。お疲れさまでした。お世話になりました。ありがとうございます。
たぶん札幌にも新しい人々が、あなたたちのコミュニティにやってくるでしょう。彼らを迎え入れて、あなたたちのやり方を見せてあげてください。仲間と一緒に物事を進めていくことの楽しさを。辛いことを分かちあうことで乗り切る踏ん張りを。ネットに価値があるのは、ネットがつなぐ両端にいる人に価値があるからだということを。札幌から、Rubyへの愛とともに。Ruby札幌の今後ますますの活躍を期待しています。フォースと共にあれ。
札幌Ruby会議01基調講演: 札幌でRuby1.9を使うということ(高橋征義)
ニコニコ動画のアカウントが無い方はRubyKaigi日記からどうぞ。
あわせて読みたい
2008-10-30(Thu) [長年日記] [Edit]
■1 ファンクション倶楽部2008秋イベント ~lambda the world~の動画を公開しました
オブジェクト倶楽部2008秋イベントでもあったもの、でUstream.tvでの配信を担当しました。当日の動画をニコニコ動画にアップロードしたのでお報せします。ust担当としての感想などはあとで書く書いた。
![Perfume First Tour 『GAME』 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41qdaM9%2BtTL._SL160_.jpg) 『手探りの私にも少しわかる気がしてる関数型言語』三村益隆, 発表資料
『手探りの私にも少しわかる気がしてる関数型言語』三村益隆, 発表資料
 『Lisp創世に見るプログラマの価値』森田秀幸, 発表資料
『Lisp創世に見るプログラマの価値』森田秀幸, 発表資料
 『Arrowのはなし』西川仁,発表資料
『Arrowのはなし』西川仁,発表資料
 LT『Rubyistのための(Lisp)入門』吉田裕美,発表資料
LT『Rubyistのための(Lisp)入門』吉田裕美,発表資料
 LT『GaUnit』須藤功平,発表資料
LT『GaUnit』須藤功平,発表資料
 LT『関数型オブジェクト指向言語Scala入門』牛尾剛&羽生田栄一
LT『関数型オブジェクト指向言語Scala入門』牛尾剛&羽生田栄一
 LT『僕の見た関数型言語』ヨシオリ
LT『僕の見た関数型言語』ヨシオリ
■2 ファンクション倶楽部のイベント会場と配信の装備
上のエントリで動画公開をアナウンスしたファンクション倶楽部の装備について簡単にまとめておきます。今回は (car (cdr '(y a))) という居酒屋での開催だったため、勉強会やミニカンファレンスを行うための設備は一切なし。すべて自分たちで調達するしかなく、各方面に大変お世話になりました。
いつも色んなイベントでUstream.tv経由の配信や後日公開される動画にお世話になっているので、自分もいちど配信をやってみたいと思っていた(録画だけは何度かやってる)。そこで今回の配信に挑戦してみた結論としては、おまえらはもっと配信担当に感謝すべき。
会場設営用ハードウェア
- 60インチの自立式携帯型ロールスクリーンは、EPSONのELPSC07。技術評論社さんのご厚意に甘えてお借りしました。
- 勤務先の会議室のプロジェクター。
- いつもは福井本社とTV会議するために使っているマイク。
- おなじくマイクアンプ(AT-MA2)。
- オフィスのフロアに転がっていたPC用の外部スピーカー(劣悪だったなあ)。
配信用ハードウェア
- まず、Mac。たしかにこれ1台あればなんとかなる。札幌Ruby会議01でcojiさんが言った通りだった。「新しい MacBook を買って勉強会の動画を配信しましょう!」
- 現場にはネット接続が無かったので、@chiba777のイー・モバイルを借りた。
- カメラは、息子が生まれた頃に安売りしてたので買った、CanonのFV M100。
- ケーブルは、DVカメラとMacの接続にIEEE1394、マイクアンプからラインへの接続にRCA型ピンジャックをステレオミニプラグの変換ケーブルを使った。
配信用ソフトウェア
たぶん定番だと思うものでなんとかなった:
- CamTwist。PinP(Picture in Pictureのことらしい。2画面合成するやつ)するのに使った。カメラは、上述のDVカメラでスクリーンを撮ってメインに、MacBook ProのiSightで講演者っぽいところを写しているものをサブにした。iSightのカメラにはときどき作業している自分のツラが映り込んでいた。修行が足りない。
- soundflower。iTunesから出る音と、ラインに接続したマイクの音声とをまとめるのに使った。最初はどうしたらいいのか皆目見当がつかなかったのだけど、LineInと組み合わせたらできた。
- さらに今回はMacが現場でのスピーカーアンプも兼ねていたので、Ustream.tvに音声を載せる以外にもモニター用の音声出力先が必要だった。これもやり方がわからなかったのだけれど、LineInをコピーしてrename、2つ起動してsoundflowerでまとめた音声をヘッドホン端子側にも出力するようにしたらできた。
配信、録画と公開
- 配信は、Ustream.tvで。
- 録画も、基本的にはUstream.tvの録画機能を利用。バックアップ目的で、DVカメラでもLPモードで録画しておいた(こちらの音声はカメラのもの)。
- Ustream.tvのflvをffmpegを使ってmp4に変換するのは、cojiさんのust2smile.rbを使えば超簡単。
- LTの動画は、全部まとめて録画しておいて、mp4に変換した後にトーカーごとにファイルを分割した。分割にはQuickTime Proを使った。分割するだけならiMovieよりQT Proのほうが手軽で簡単だと思う。これもcojiさんのエントリを参考にした(今回は変換は終わってるので、切り出して保存するだけ。
- あとはニコ動にアップロードすればOK
- 配信の音声はマイクからのライン入力を使ったので、ひょっとするとustのほうが音はよかったかも。現場ではスピーカーが劣悪だったので。
- 映像はデフォルトの11fpsにしてたんだけど、LTでは映像が遅れていた。cojiさんは5fpsぐらいにしてるとIRCで誰かに教えてもらった。なるほどね。録画ではなんともないみたいなので、このへんはどうなんだろう。
配信から公開までのノウハウは、札幌Ruby会議01のcojiさんのLTを通じて知った。coji++
感想など
今回はミムラくんの発表の途中で一度イーモバの接続が切れたので、彼の発表だけテープからサルベージした。イーモバが切れたのはこのときだけで、あとはずっと安定してた。
ほんとうはTechTalk.jpへの敬意を表して、拙いながらも配信・公開までこぎつけられた結果としての動画公開アナウンスもtechtalk.jpでやりたかった――のだけど、Movable Typeの使い方がまったくわからず、即刻諦めてしまった。ざんねん。
まとめると、いまや配信と録画が公開されることが空気のように期待されるIT勉強会やカンファレンスだけれども、気は遣うし作業も(自動化できる部分はあるにしても)それなりにあるので、やっぱり大変です。みんなもっと配信作業を担ってくれる人たちに感謝しよう ><
でも、やってみると面白いのは確かで、配信好きをこじらせると以下のようなブースになってしまう気持ちが少しだけわかる気がした。

(写真はcocooooooon撮影のものを借りた) また機会があったらやってみたい。








 リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大)
リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大) 『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』
『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎)
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎) 実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘)
実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘) The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ)
The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ) アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未)
アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未) アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎)
アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎) インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修)
インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修)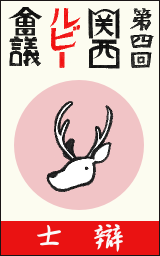



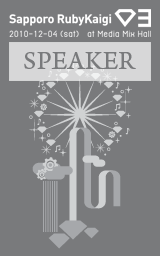






○ zunda [いち編集としては尻を叩いてくれる人が欲しいです。この記事いつまでに見てっ!って。…ってRSpecではそれは僕の役のは..]
○ ささだ [具体的な問題は,積極的に引っ張っていくひとが居ない,ってことだと思います.で,協力するためのとっかかりが欲しい,とい..]
○ かくたに [感極まった人が突入できるようにできればいいのかな。あー。なんかそういうのは数少ない「私がRubyにできること」のひと..]