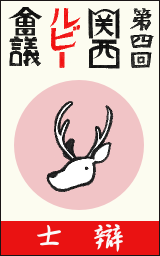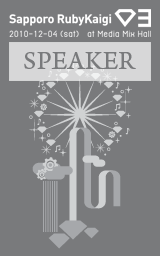2004-06-10(Thu) [長年日記]
■1 「ダイコン時代の設計手法 - ロジックをどこに置くのか」
酔っ払ったときに私がtakaiさんといつも話していたのはこの話題。
そうはいっても「Tell, Don't Ask」的な手法を取り入れる余地はあると思う。が、私にはサービスに置くべきロジックと、エンティティに置くべきロジックの判断基準も示せなければ、各々のロジックを示す名前もつけられないので、言葉が続かない。時間ができたら少し他人の褌で独り相撲をとろうかな、とは思っているけれど。
私のことはどうでもよくて、ひがさんによるこれら「実践ダイコンシステムデザイン」、というか「Expert One-to-One DICon Design and Development」(まさにOne-to-One!)のシリーズは必読。
■2 Safariに入ったらmanningが充実する罠。
MEAP*1なんてのも始められてしまった。Amazonでの購入すらためらわれる。Safariで書籍費削減の野望は潰えてしまうのか……。
Manningのサイトでのラインナップをみると、イキオイがあるなー、と思う。
Safariトークンの謎を解く
わーい。貧乏性なので、ビビってまだひとつも使ってなかったので、助かりました。規約ちゃんと読め、って感じだが。
*1 Manning's Early Access Program。出版前に読めたり色いろあるようだ。
■3 「ダイコン時代の設計手法 - 例外処理」
otsukaさんのところに寝ぼけたコメントをなすりつけたりしているので、以下も寝言のようなものだが:
折りしもIBM dwにも「Java theory and practice: The exceptions debate」が出ていたところ(「Javaの理論と実践」シリーズなのでいずれ翻訳されるでしょう)。検査例外派、実行時例外派、中庸派と整理されている。
私は「catch禁止。間違いない」とまでは踏み切れない、中庸派という名の日和見主義者なので、catchしたうえで機能としてやることがある(再実行とか、プレゼンテーションに特殊な表示をさせたいとか。項目40*1参照)のなら、検査例外を使いたい。といっても、この場合は注意深く設計する必要があって、うっかりすると項目39*2違反になってしまう。状況によっては設計者間での意思疎通のコストもバカにならない(これは分岐か?例外か?)。つまり、「よほど例外の設計に自信のない限り」のケースなわけだ。道理で。火傷したこと一度ならず。
ちなみに上記の「項目:nn」は『Effective Java』。イマドキはこのあたりに関しても、もっと良い(というのは日本語が読みやすい)書籍はあるのかな?
■4 higaさんによるダイコン時代の設計方法 - tpircs
tpircsさん作成(偉い!!)。
 リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大)
リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大) 『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』
『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎)
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎) 実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘)
実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘) The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ)
The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ) アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未)
アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未) アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎)
アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎) インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修)
インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修) アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎)
アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎) JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)
JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)