2004-01-19(Mon) [長年日記]
■1 「@IT:緊急提言:Webサービスの光と陰を考察する(3)」
2ヶ月を要した「緊急提言」の着地点はデータ指向のお題目として馴染み深いOne fact in one place、データは安定している/プロセスは変動する、全社横断的なITシステムガバナンス、「設計」段階が大切、データのクレンジング(!)と維持、などなど。
なるほど、そりゃあWeb Serviceは広まらんわな。DOAでサブシステム間のプロトコルが標準化されてるだけじゃあないの。それも進歩といえば進歩ではあるが。年々歳々技不同、年々歳々人相似。
ピンポンダッシュ的言説を弄するならば、これもおそらく総論としてはEnterprise Integration Patternsと同じなのだろう、たぶん。とはいえ、妄想するに、あちら(EIP)は、出発点が「"One fact in one place"って無理くね?」というところから出発している(ように思える)のに対し、緊急提言では必要条件になっているような。私は「無理くね?」派だ。
そして、自分でも考えが整理できていないので当たり屋的に「そんなことより聞いてくれよ>>1よ」から引用:
確かに変わるのはプロセスだろうが、プロセスが変わってもデータが変わらないのは本当に可能だろうか。プロセスが変わっても変わらないデータというものを考えることが難しいのではないかと思うのだ。感覚的には抽象化したデータほど不変なものになるが、具体化したデータほどプロセス(処理)に影響を受けやすい。なぜならプロセスがないとデータを具体化できないからだ。だからこそ「オブジェクト指向(データ+プロセス)」という話があったりするんじゃないのかなと思っている。
——我が意を得たり、である。それ以上踏み込めない自分が哀しいね。
とまれ、「SOAはDOAと親和性が高いのでOOイラネ」とうっかり言ってしまう人たちが居るのもむべなるかな、ということはわかったような気がする。気がするだけかも。
で。MessagingでIntegrationというのは、むしろOOだと思うんだがなー。オブジェクトはメッセージ反応して、メッセージの種類応じて適切に自立的に振舞う、んだもんね。私も「考えれば考えるほど、サービス指向と(分散)オブジェクト指向の違いが分からなくなる」。
何の考察も結論も提言も無いまま、この項終わり。
■2 TrackBackの仕様書(日本語訳)を読む
シンプルですな。TrackBack用のURIのことをTrackBack ping URLと云うのだな。XML-RPCとRESTの違いがイマイチわからないが、それはまあ追々。
PukiWikiから撃たれたTrackBackをこっちから辿れない?
文字列エンコードの問題っぽいっが、このサイトもtDiary最新版で無いから問題を切り分けにくい。とりあえず、cvs -z3 up -dP.
追記
相手のサーバが落ちているだけかも。回復待ち。→単に落ちているだけだった。無事辿れる。
 リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大)
リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大) 『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』
『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎)
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎) 実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘)
実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘) The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ)
The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ) アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未)
アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未) アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎)
アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎) インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修)
インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修) アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎)
アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎) JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)
JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)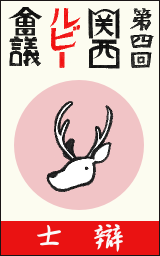



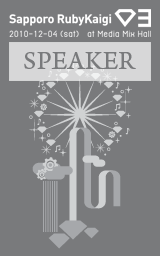






すみません.まだコミットしとりません.たださんにもせっつかれてるんですよ,実は…