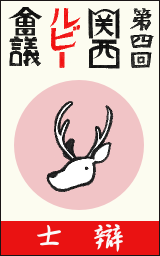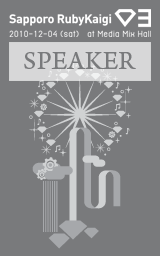2010-04-14(Wed) [長年日記]
■1 RubyKaigi2010に関連していま思っていること
……は、Web日記に書くんじゃなくて古式ゆかしくメーリングリストというころに投稿してました。日本Rubyの会MLというメーリングリストがあるのです。
■2 Pivotal TrackerのGetting Startedの翻訳
Web日記じゃないところに書いたものつながりでお知らせ。
必要に迫られて以下をリリースしました:
私たちの役にたったので、他の誰かのお役にも立つといいなと思ってます。Happy Estimating & Planning!
 アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~
アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~
毎日コミュニケーションズ
¥ 3,360
そういえば、『アジャイルな見積りと計画づくり』は4刷が決定したそうです。読んでいただいて、周りに口コミで紹介してくださっている皆さまのおかげです。ありがとうございます。
■3 2年前の動画をいま見てくれた人がいたということとRSpecのMacroについて
2008年の2月の雪がしこたま降っていた札幌で話をしたときの動画を、最近観てくれたことをはてなに書いてくれた方がいて、さらにご自分でいまどきのRSpecの使い方をふまえてリファクタリングしてくれていた。ありがたいことです。Ruby札幌++
そういう意味では、先日id:hyoshiokに呼び出されてお話しした動画とか、「解読」とか言うわりにはたどたどしい限りで、youtubeの分割ファイルのサムネ全部貼ってあるとか晒し者にもされるにしても程があるだろうとも思うんだけど、「未来のいつか」誰かに届くことがあるかもしれないと思う今日この頃。
話を戻して。で、上記のsubjectやnested contextを使ったリファクタリングの書き方で私がいま何かお返しできることがあるかなあ、とぼんやり考えていたところ、たまたまミーティングとミーティングの合間のビミョウな時間ができたのでちょっとやってみた。こういう書き方もできますね。
describe Game, "#score" do
include BowlongGameMacro
context "すべてガターの場合" do
play_game { 20.times { roll_gutter } }
score { should == 0 }
end
...
context "スペアの場合" do
play_game do
roll_spare
roll_on_frame(4, 3)
16.times { roll_gutter }
# (10 + 4) + 4 + 3 => 21
end
describe "スペアの次の投球で倒したピンがボーナス加算される" do
score { should == 21 }
end
end
これはRSpec界隈ではMacroと呼ばれている手法(たとえば、RailsCastの157: RSpec Matchers and Macros)を、こじらせた感じ。全文はこんな感じ:
さいしょに"Rspec Macro"って聞いたときには「えっ。何それ」って思ったんだけど、説明をみるとModule#includedとObject#extendを使ってるだけでした。
えっと、いまの時点でこれについて議論できるだけの準備が私にはありません。これは素晴しいものだよ諸君今日からみんなこう書くべきだよとか自分でも思ってません。トレードオフだよ、みたいなのもあんまり興味ないです。まずは「単なる成功したプロジェクトと失敗したプロジェクトのお話のリスト」を集めるのが先だなあと思ってます。
いまの時点での自分じしんにとっての収穫は『Growing Object-Oriented Software, guided by Tests』の"Chapter 21: Test Readability"のトピックとのつながりが見えはじめたことーー見えはじめた、というだけでそのの続きはまだ無いんだけど。
『Growing Object-Oriented Software, guided by Tests』は冒頭で紹介してある楽天さんでの講演でも少し言及したけどほんと良い本で、このタイトルだけでライトニングトークやれると思ってる。
どれぐらい良い本かというと、もしも何でも可能な世界で、私がid:t-wadaと一緒に一冊だけ技術書を書いていいと言われて、それを達成できたら(これは可能世界の話ですからね!)、できあがるのはこの本だと思う。そのときのサンプルコードはRubyだね。Steve Freeman とNat Pryceは「よく勉強している」ので、全編とおして私好みのキラーフレーズ満載。"Expect Unexpected Change"、「テストコードにはwhatを、プロダクトコードにはHowを(要旨)」、"Test-driven development combines testing, specification, and design into one holistic activity"。この本を読むことを通じて「TDDとTiDDの違いについて自分なりに整理がついた」のでした。おすすめ。

 リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大)
リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大) 『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』
『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎)
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎) 実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘)
実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘) The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ)
The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ) アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未)
アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未) アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎)
アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎) インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修)
インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修) アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎)
アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎) JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)
JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)