2005-02-23(Wed) [長年日記]
■1 近況
いつまでもage+=1が一番上にあるものなんなので、更新しようと思う——のだが、ひとくちゲロはmixiに書いてスッキリしちゃっているのと、すさまじく大きなToDo(「人生の転機。鬱」)があるのでこちらの更新はままならず。
大きめのToDoを指して「大トド」と呼ぶならわしのある界隈もあるようだけれど、私にとってこんかいのToDoはさしずめ「クジラ」だな。
■2 Ruby hotlinks 五月雨版
Ruby hotlinks 五月雨版の「日記」カテゴリに補足されている。どなたかがリクエストしてくれたからだろうか? わーい。
アジャイルな人からアジャイルなRubyの人へ、が私の目標。
Ruby方面といえば個人的にはChizzleは祭になってしかるべきなのだれど、まだwxwinもapt-getしていない体たらく。
■3 DIが良いか悪いかなんて話はもうしないよ。
日経ITProで取り上げられて、随所でまた話題になりつつあるDI。バカが征くでもここのところ興味深いエントリが続いていた。
日経ITProの香ばしい読者コメント欄はさておき、もう良い悪いの話ではないと思う。ひがさんはDIそのものを超えて、星ぼしの荒野を目指している。
地上に残された我われは、ダイコンというGenericでのっぺりした「基盤」をいかに立体的に使いこなしていくか、が大事だと思う。ダイコン・ベストプラクティスとでも呼べばいいのかな? 使っている人達のウェブロとかで見解は散見できるけれど、まとまった記事ってないよな。
「Spring + Hibernateで」とか「S2 + S2DAOで」とかそういうのじゃなくて、もっと設計っぽい話が読みたい。MF記事では棚上げにされている、ライフサイクルとAOPの話題も十分には議論されてないような印象。AOPについてはシゲル・チバのプレゼン(PDF)が印象的。
だらだらと書き連ねたけれど、このセクションのタイトル元ネタ(PDF)であるところの咳さんはDI懐疑派なんだけど。DIについてのエレベータステートメントはいまだに用意できてない。
ちなみに弊社標準ダイコンはS2です、と勝手に言いきってみる。もう納品して稼働してるみたいだし。
 リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大)
リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大) 『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』
『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎)
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎) 実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘)
実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘) The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ)
The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ) アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未)
アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未) アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎)
アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎) インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修)
インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修) アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎)
アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎) JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)
JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)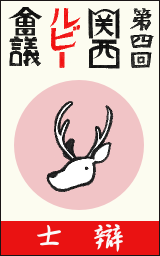



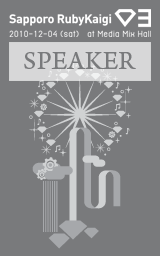






えー悪役っぽい。DIはOOPの基本的なテクニックな気がするのと、コンテナが必要になるなのはそういう言語/環境だからだ、というのと、テストの帽子をかぶった私にはコードも設定ファイルもいじったら信用しないよ&Mockの試験はかなり単体試験じゃん、なによりデベロッパをフレームワークをつくっていい上手な人と、それを使うだけの上手じゃない人にわけるのもいやんなだけですよ。ってかなり懐疑派なのか?DInoは疑ってないですよ。
あー、息切れして投稿しちゃった。最後は、DIそのものは疑ってないですよ。です。
悪役だなんて滅相もございません。ありがとうございます。色いろ思うところがあるのでしばらく考えさせてください。
DIコンテナがいらない言語/環境なんてあるんですか?<br>たしかRubyにもDIコンテナあったとおもうんだけど。<br>勉強のために教えてください。
「DIを必要とする状況へと強く引き寄せられている言語/環境」とでも読み替えていただければよいかと思います。
>テストの帽子をかぶった私にはコードも設定ファイルもいじったら信用しないよ<br>これって良くわからないんですが、試験は本番環境とコードも設定ファイルもいっしょにしてやらなければ意味がないということでしょうか。とするとユニットテストが出来なくなると思うのですが、それってXP的にどうなんですか?<br>>Mockの試験はかなり単体試験じゃん<br>ん?Mockって単体試験するために使うんじゃないんですか?<br>>なによりデベロッパをフレームワークをつくっていい上手な人と、それを使うだけの上手じゃない人にわけるのもいやんなだけですよ。<br>えーと、DI使うとなぜそうなるのかが良くわからないのですが。