2005-12-23(Fri) [長年日記]
■1  誰がアジャイルを「殺す」のか?
誰がアジャイルを「殺す」のか?
そのリストには自らが関わるプロセスの「軽量化」のエクスキューズに利用する、スケジューリング(プランニングではない)やドキュメントが嫌いだったり苦手だったりする開発者をはじめ、様ざまなものを挙げることができる。個人的にはこのリストに「魂に響かない翻訳」を加えたい。判型が既存のXPシリーズと同じ(原書より一回り小さい)なのは携帯しやすいので嬉しい。
PofEAA第9回では勝手に第23章をサマるよ。
2005/12/28追記
言い訳がましく補足しておくと、いまのところ翻訳はそんなに悪いとは思ってません。試しに第23章を全文自分で訳してみて痛感したのだが、(勿論)私の負け。ただ、この翻訳には原著を読んだときのような、心が震える感じを受けない。本書は、アジャイル開発に興味があるすべての人にとって、とてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとても大事な一冊だと思っている。なので、原著から感じた力強さと率直さと、ラヴ&ピースを、日本語でも感じたい。そう思い・表明することは贅沢なのだろうか。ワガママなのだろうか。禁じられたことなのだろうか。
(この項は、翻訳を読了した後のエントリに続く。今は他に「あとで書く」べきものが多すぎる)
■2 『Rubyist Magazine 0012号』リリース
出ました。いつもいつもありがとうございます。これから読む。クリスマスイベントのMatzセッションのレポートを寄稿すれば、時期的にも宣伝になったのに、失敗した。って寄稿するにも、まだレポートを書いてないんだけど。
- 高橋さんの巻頭言は、Ruby業務チーム出現の予言と基盤チームの持つ希望について。わ。ぐRubyって書いてある(w
- Rubyist Hotlinks: LLDNの「羽」のデザインが!!
- Rails: ActiveHeartとRailsプラグイン。おっと、著者がgorouさんではないか。
- qwikWeb: GroovyMarkup/Builder作戦は「わびさび」方式には入らないのかな。ジェームズ・クラーク式記法。老人力としてのユニットテスト(!= TDD)。
- 他言語探訪がGroovy(みずしまさん)だ。Jim Weirichが「Ruby版GroovyMarkupを作成された方」という扱いなのがちょっと寂しい。
- ...
 リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大)
リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大) 『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』
『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎)
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎) 実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘)
実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘) The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ)
The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ) アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未)
アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未) アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎)
アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎) インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修)
インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修) アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎)
アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎) JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)
JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)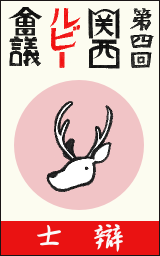



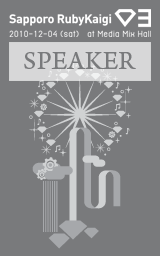






申し訳ないです。Ruby版GroovyMarkupがあるということを紹介するのが主眼だったのと、Jim Weirichという人がどういう方なのかあまりよく知らなかったため、ああいった形になってしまいました。 > Jim Weirichが「Ruby版GroovyMarkupを作成された方」という扱いなのがちょっと寂しい。