2005-06-24(Fri) [長年日記]
■1 「Rubyワールドは関わる人に金の匂いがしない。」
肉食系開発者のまさたかさんのコメントを部分的に引用:
- Rubyワールドは関わる人に金の匂いがしない。->これはいけない。みんな遊んでるんじゃないんだから。。。遊びで終わらせるならいいけどね。(攻略)
- 最後に私見。Railsを「輸入」してよろこんでるだけなのはいかがなものかと。ちょっと楽しくないよね。そんなこと無いのかな?言語仕様を握ってる人も近所にいるんだし、AOT&VMを今つくろうとしているんだから、Ruby Enterprise Editionとかやったらいいんじゃないかな。面白いと思うんだけどな。
引用終わり。これに対して「物申す!!」と言えるような見識も実力もないので、チラシの裏に書くべきような話。
いまのところRubyには「儲ける構図」が無い。金の匂いがしない。言語仕様とか処理系というよりは、エコシステム的な課題という印象も強い*1。エコシステム的な課題というのは、モダンIDEがあったりとか、分散トランザクションとか非同期メッセージングとか。Java界はエコシステムが充実している(JSRはちょっとアレだけど)。
エコシステム的な視点からは、Ruby界にとってRailsは「事件」なのだと思う。gemsを前面に出して来たりとか、Fowlerも『Language Workbenchs以下略』(この記事はヤヴァイ。kdさんがんがれ)でちょっとだけ言及しているような、メタプログラミング——DHH曰く、『オレはそれを「便利だね」と呼ぶね』のやりすぎな使い方とか。
唐突にまとめると、Rubyの威光がギョーカイを覆いつくす!!となることを望みはしないのだけれど(なったら面白そうだけど)、私ぐらいの人間でもRubyでおいしいご飯を食べられるぐらいになる日がくるといいなあ、と思うし、そうなるようにコツコツやっていこうと思います。
Python界にはPEAK(Python Enterprise Application Kit)というのがあるらしいよ、とKKDさんに教えてもらったけど、普及とか利用はどれぐらいされてるのかなあ。
エコシステム
エコシステムって便利でいい言葉で、重要だと思うんだけど、アジャイル界隈では見事にスベったね。
*1 勿論、言語仕様や処理系も無関係ではない。比重というか相対的な話。
 リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大)
リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大) 『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』
『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎)
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎) 実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘)
実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘) The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ)
The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ) アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未)
アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未) アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎)
アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎) インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修)
インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修) アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎)
アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎) JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)
JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)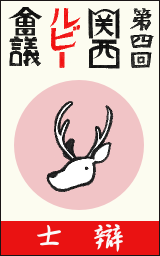



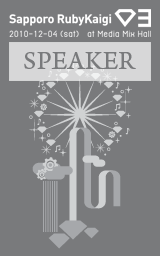






「望みはしない」のであれば、実現しない
ということかなと。なんで望まないのかな?というのが根源の疑問です。PHPができたことはRubyにもできると思うけどね。
ぎゃふん。「なんで望まないのかな」、仰る通りです。ただ、いまの私にとってはこの望みは「明日、学校が火事になって試験がなくなればいいのになあ」と大差ないようにも思えたからだと思います。精進します。
Seasarプロジェクトは、パブリックに「望む」ようになって1年です。たった1年ですよ。「すばらしい技術が普及するとは限らない」だから「マーケティングが大事」とはよく言われることですが、その逆はどうか。普及しないのはマーケティングが下手なのでなく、やってないんじゃないですかね。「望んでない」のではないかと。もちろん「望む」=「マーケティング」とは限りませんので。