2004-02-18(Wed) [長年日記]
■1 「ドメイン特化言語」がいいな
2004-02-17 (火) 13:42:40 kdmsnr : specific を 「特化」とするか「依存」とするか。どっちがよいのでしょう。
同じ物事の裏表なのだが、「ドメインに依存して作成された言語」というよりは「特定のドメインに特化して作成した言語」のほうがポジティブな印象。「依存」だと"dependency"に思えて、ちょっとネガティブな感じ。単に個人的な感覚の問題だろうか。
「極力、UML訳語集に忠実に訳していきたい・・・。」とのことなので、MDAでのPSM(Platform Specific Model)に「プラットフォーム依存モデル」と訳語が当てられていることを踏まえての措置だとは思う。が、UML訳語集を見てみると、
- specific
- 特化
- Platform Specific
- プラットフォーム特化
- Platform Specific Model
- プラットフォーム依存モデル
そもそものPSMの訳語が不適切な気も。おそらくはPIM(Platform Independent Model:プラットフォーム独立モデル)との対比で「依存」という言葉を選んだのだろう。PSMは確かに「依存モデル」ではある。が、送り手の思いとしては「特定プラットフォームに依存しちゃうモデル」というよりは「PIMから特定プラットフォームに特化して(自動で!!)生成したモデル」ではなかろうか。
HikiにもTrackBackができるといいのに
bliki_jaは、TrackBackが必要な存在だ。本家blikiがその出自からしてウェブロ+Wikiなのだけれど、この場合はFowlerタン専用という面が強い。しかし、bliki_jaはそうではない。blikiを翻訳するにあたって、バザールに翻訳しようというコンセプトをブチあげて、その手段としてWiki(ここではHiki)が選ばれている。通常のWikiなら、思うところは該当Wikiページに書き込むのが筋だろうけれど、bliki_jaはそうはいかない。でもbliki_jaはWikiである必要がある……。まとめ:
- 記事ベースで誰でもイジれる必要がある(バザール翻訳)、
- けれど/であるがゆえに、第三者が議論・感想・質問・疑問を書くには向かない(あくまで記事翻訳だもん)
このゴルディアスの結び目(なのか?)をぶった切るのは、HikiのTrackBackプラグインだと思う。
■2 どっちのコード・ショー(5)
自分なりにまとめてみた。一度、作業途中で消失したので遅くなってしまった:
——って、選択肢は3つあるので全然「どっち」じゃないんですけど。
追記: StringBuffer in Tiger
実装が変わってるよ……。
 リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大)
リーン開発の現場 カンバンによる大規模プロジェクトの運営(Henrik Kniberg/角谷 信太郎/市谷 聡啓/藤原 大) 『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』
『なるほどUnixプロセス ― Rubyで学ぶUnixの基礎』 SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎)
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK(西村 直人/永瀬 美穂/吉羽 龍太郎) 実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘)
実践テスト駆動開発 テストに導かれてオブジェクト指向ソフトウェアを育てる(Steve Freeman/Nat Pryce/和智 右桂/高木 正弘) The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ)
The RSpec Book (Professional Ruby Series)(David Chelimsky/Dave Astels/Zach Dennis/角谷 信太郎/豊田 祐司/株式会社クイープ) アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未)
アジャイルサムライ−達人開発者への道−(Jonathan Rasmusson/西村 直人/角谷 信太郎/近藤 修平/角掛 拓未) アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎)
アジャイルな見積りと計画づくり ~価値あるソフトウェアを育てる概念と技法~(Mike Cohn/マイク コーン/安井 力/角谷 信太郎) インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修)
インターフェイス指向設計 ―アジャイル手法によるオブジェクト指向設計の実践(Ken Pugh/角谷 信太郎(監訳)/児島 修) アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎)
アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣(Venkat Subramaniam/Andy Hunt/木下 史彦/角谷 信太郎) JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)
JavaからRubyへ ―マネージャのための実践移行ガイド(Bruce A. Tate/角谷 信太郎)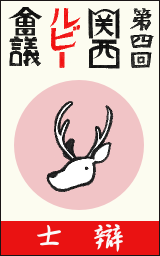



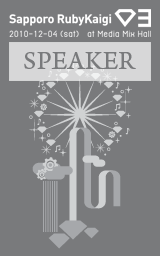






特化にしますた。